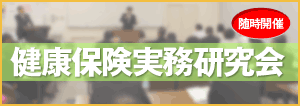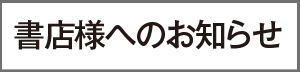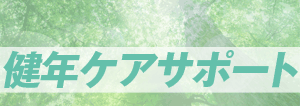健保・年金相談室
社会保険労務士の方や各団体の相談員、専門家の方は、日頃、多方面から種々の質問を受けています。ここでは健保組合、共済組合、協会けんぽの職員の方、年金実務に携わる方が業務の参考になる事例を取り上げ、わかりやすく解説していきます。
2024.12.16UP
2002年1月16日に第1回目の社会保障審議会年金部会が開催され、2024年12月10日には第23回を迎えました。以前紹介した障害年金制度の見直しの他にも、被用者保険の適用拡大と第3号被保険者への対応や遺族年金制度についての議論がなされてきました。他にも、在職老齢年金の基準停止額の見直しなど、2025年の通常国会に向け、年金改革関連法案が提出される予定です。今回は、その中の一部の改正案を見ていきます。
働き方に中立的な制度の構築を目的とする改正案
(1)被用者保険の適用拡大いわゆる「年収の壁」と第3号被保険者制度について
厚生労働省は、2026年10月に「106万円の壁」を撤廃し、2027年10月に企業規模による加入要件を撤廃すると発表しました。これにより、週20時間以上働く人は原則として社会保険の被保険者となり、保険料を納めることになるため、第3号被保険者の縮小につながります。
(2)在職老齢年金制度について
現行の在職老齢年金の支給停止の基準額の50万円では、高齢者の働く意欲をそいでいる現状を踏まえ、この基準額を62万円か、71万円へ引き上げるか、いっそ撤廃するか検討されています。
と同時に、現在の厚生年金の標準報酬月額の等級の上限 (65万円) を引き上げることによって、保険料収入の増加と受給できる老齢厚生年金額の増加を図ることの議論も行われています。
ライフスタイル等の多様化への対応となる改正案
(1)遺族年金の見直しについて
現行の遺族厚生年金の男女差を解消し、60歳未満の子のない配偶者(男女とも)には、5年の有期給付とする案が出されました。その場合、現行に比べると支給期間が短くなる分、「死亡時分割(仮称)」や「有期給付加算(仮称)」を創設して、その減少分の生活保障を図る配慮措置もとられました。他にも、現行制度の生計維持要件のうち収入要件(収入850万円未満)も廃止し、「中高齢寡婦加算」も段階的に廃止するなど、男女や収入の差を解消していく方向です。
なお、現在の受給者や高齢の方及び18歳未満の子のある配偶者への遺族厚生年金は、現行のまま、変更しない予定です。
(2)3人目の子に係る加算
子に係る加算を、厚生年金・基礎年金のいずれにおいても年金の種別に拠らない共通の制度とし、現行では、3人目が減額されていますが、子の出生順位にかかわらず、一律の金額を加算してはどうかと検討されています。
その他 期間延長等
(1)離婚時年金分割の申請期間の延長
離婚時の年金分割は民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が現行の2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年金分割の請求期限についても現行の2年以内から5年以内に伸長すると検討されています。
(2)国民年金の納付猶予期間の時限措置の延長
30歳以上50歳未満 の者が最初に追納期限である10年を迎える令和8年以降に改めて納付猶予制度の最終的な追納動向等を把握すること とし、今回の年金制度改正においては以下の通り進めてはどうかと検討されています。
- 被保険者の対象年齢の要件は現行通り。(被保険者が50歳未満であること。)
- 令和12年6月までの時限措置を令和17年6月まで5年間延長。
出典、厚生労働省、社会保障審議会(年金部会)の資料
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.11.1UP
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証に替えて、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するため、協会けんぽ等の保険者から被保険者や被扶養者あてに、健康保険の資格情報のお知らせやマイナンバーの登録の案内などの通知が送付されています。
ここでは、協会けんぽの通知を見ていきますが、健康保険組合や共済組合等については加入している健康保険組合や各共済組合等に問い合わせます。
協会けんぽが発行している資格情報のお知らせ
令和6年9月以降、協会けんぽから会社(事業主)経由で被保険者とその被扶養者個人分の「資格情報のお知らせ」が送付されています。これにより、加入者の健康保険の資格情報を把握できます。また、用紙の左下にある「資格情報のおしらせ」は令和6年12月2日から医療機関等を受診する際必要となる場合があるので、点線で切り取ってマイナンバーカードと併せて保管します。
マイナ保険証を利用するためには、正確なマイナンバーの登録が必要なため、「1.マイナンバー下4桁の記載があるお知らせ」と「2.マイナンバー下4桁の記載がないお知らせ」の2種類が送付されています。
1.マイナンバー下4桁の記載がある場合
協会けんぽに登録されているマイナンバーの下4桁が表示されているので間違いがないかマイナンバーの番号を確認します。
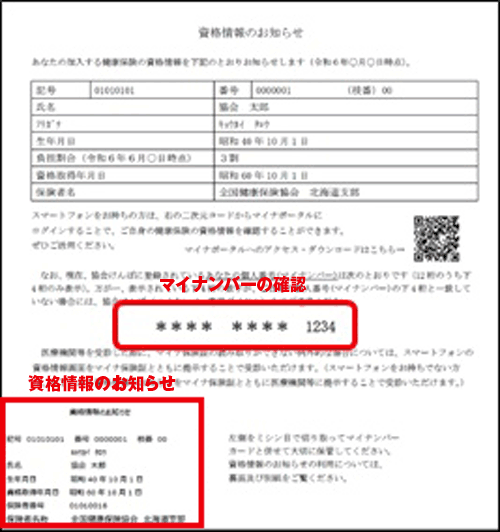
2.マイナンバー下4桁の記載がない場合
協会けんぽにおいて、マイナンバーが登録されていない又は登録されたマイナンバーを確認する必要がある場合には、マイナンバー下4桁が記載されず、「マイナンバー登録申出書」が同封されています。
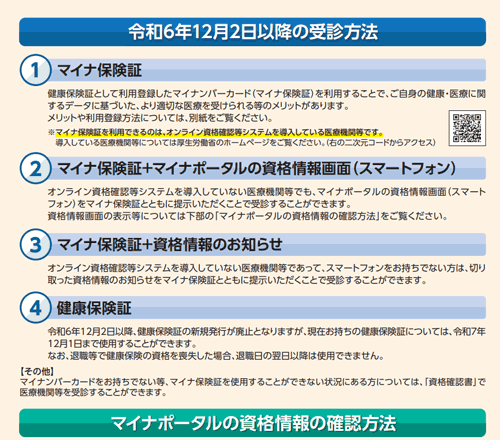
令和6年12月2日以降の受診方法
スマートフォンからマイナポータルにログインして、資格情報画面で自身の健康保険の資格情報を把握できます。また、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等の場合に、マイナ保険証とともに 提示することで医療機関等を受診することもできます。 マイナポータルにログインできないときは、切り取った「資格情報のお知らせ」を使います。
出典 協会けんぽのホームページ
日本年金機構に提出する届書の様式変更
令和6年12月2日以降、日本年金機構に提出する「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が設けられます。新たに被保険者や被扶養者になる人が「資格確認書」を必要とする場合は、「□発行が必要」にチェックを入れて提出すると協会けんぽから「資格確認書」が発行されます。
変更となる届書(一部)
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
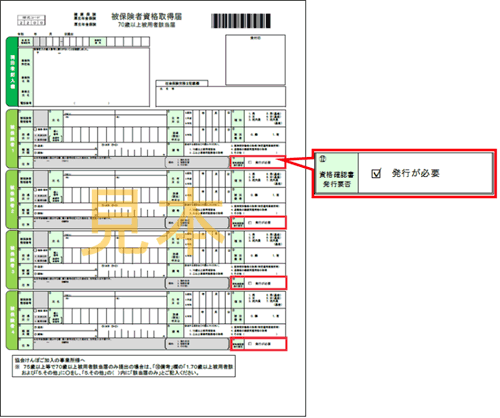
・健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
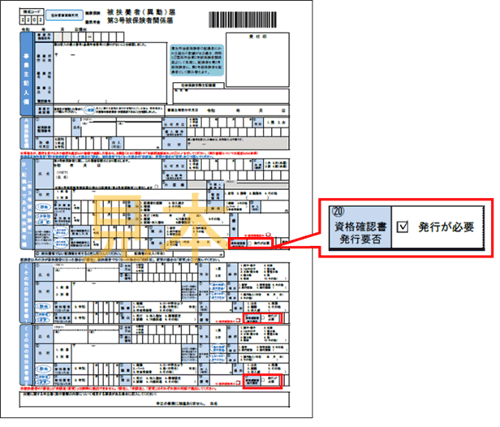
出典 日本年金機構のホームページ
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.10.1UP
1.社会保険
令和6年10月から健康保険・厚生年金保険の適用が51人以上の特定適用事業所で働く短時間労働者に拡大されることがテレビCM等でも盛んに流れています。短時間労働者とは、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である人のうち、以下の条件にすべて該当する人となります。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(残業代・賞与等は含まない)
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生は含まない)
これにより、同時に2ヶ所以上の事業所で被保険者資格の取得要件を満たした場合、二事業所の勤務該当となります。被保険者は、いずれか一つの事業所を選択して、その事業所を管轄する年金機構の事務センター等に「被保険者所属選択・ 二以上事業所勤務届」を届出る必要があります。健康保険の保険者(協会けんぽと健康保険組合など)が二以上あり、健康保険組合を選択する場合は、事務センター等及び選択する健康保険組合にも届出が必要です。標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した額で決定され、それぞれの報酬月額に基づき、按分して保険料が徴収されます。
なお、特定適用事業所が、国・地方公共団体等である場合の手続きについては、該当の保険者等に確認します。
2 労災保険について
労災保険については、そもそも雇用保険や社会保険のような加入基準がなく、個人が加入手続きをする必要はありません。勤務を開始した時、強制的に全ての従業員が加入したものとみなされ、労災保険の保険料は、全額事業主負担となります。毎年7月10日までに労働保険の年度更新をして、労災保険料と雇用保険料を合算した労働保険料を納付します。
なお、令和2年9月の改正で、複数事業労働者やその遺族等への労災保険給付額は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として決定されています。
3 雇用保険について
雇用保険の加入基準は、「1つの事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用する見込みがある」場合です。たとえば、今回の社会保険の適用拡大により、2以上事業所勤務該当者になったとしても、雇用保険は重複して2以上事業所で加入できず、原則は賃金の高い方の事業所でのみ加入となります。
最後に、雇用保険から事業主へのキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」があります。これは、新たに従業員を社会保険に加入させるとともに収入増加などの取組みを行った場合に、助成金が受けられ、今回の社会保険の適用拡大に伴い新たに加入対象となる 労働者に対して手当等の支給や週の所定労働時間を延長する等の取組みも対象となる場合があります。詳細は、都道府県労働局またはハローワークに問合せます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.9.2UP
2024年7月30日17回社会保障審議会年金部会において、障害年金制度の【現時点で議論が求められる課題】として次の5点が示されました。
1.初診日要件について
現行では、障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金か厚生年金(共済組合)かいずれの被保険者であったかで受給できる年金が決まります。過去に長期に渡って厚生年金保険料を納付していても、退職後の初診日が国民年金の被保険者であれば障害厚生年金を受給できません。その対応として、延長保護(被保険者資格喪失の一定期間内であれば、被保険者資格喪失後の保険事故発生も給付対象にする)と長期要件(厚生年金保険料の納付済期間が一定以上あれば、給付対象にすること)を認めるか否かの議論がなされました。延長保護を認めるにあたっては、短期間での離職等により国民年金と厚生年金を頻繁に異動する被保険者の場合や社会的治癒など初診日の特定が難しい事例が増えることが予想されるなど意見が出ました。
2.事後重症の場合の支給開始時期について
事後重症とは、障害認定日において障害等級表に定める障害の状態に該当しなかった場合でもその後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに症状が重くなり、本人が請求した日に受給権が発生するケースです。障害状態に該当すれば、請求した日の翌月から支給となります。この事後重症請求の支給開始年月を、客観的に受給要件を満たした日(障害等級に該当した日)にまで遡及してそこから支給開始とする案が検討されています。
3.直近1年要件について
直近1年要件について、現在令和8年3月31日が当該措置の期限となっていますが、次期制度改正に向けて、これまで同様に更に10年間の延長をするかどうか検討されています。
4.障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱いについて
現行では障害基礎年金受給者の国民年金保険料は法定免除となりますが(希望すれば納付も可能)障害の状態が65歳前に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された場合、免除されていたため減額された老齢基礎年金を受給することになります。そこで、障害年金受給中の期間を免除ではなく保険料納付済期間に算入して計算することで、現行より増額された老齢基礎年金の受給とすることが検討されています。
5.障害年金と就労収入の調整について
現行では、国民年金法30条の4(20歳前の障害基礎年金)に基づく障害年金以外は、原則として、就労をして収入を得たとしても、直ちに支給停止になったり減額されたりすることはありません。また、身体の障害で永久認定の障害年金を受けている場合は、障害の程度の診査もなく収入がいくらあっても障害年金は支給され続けています。しかし、精神などの障害年金では、更新時の就労状況によって、障害等級の見直しが行われ、その結果として年金額の減額や年金支給の打ち切りが行われることがあります。このような状況を踏まえ全体的に就労収入と障害年金の調整について検討されています。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.7.3UP
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止されマイナ保険証へ切り替えられます。発行済みの健康保険証については、廃止後最大1年間は、従来通り使用できるよう経過措置が設けられ、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方については、「資格確認書」を用いて医療機関等を受診することが可能です。
その準備で、協会けんぽや健康保険組合等の保険者や医療機関等でマイナ保険証利用促進の広報活動が行われています。
協会けんぽのホームページでは、健康保険組合連合会と共同作成した『使ってみよう!マイナ保険証』の動画が紹介されていて、マイナ保険証のメリットや使用方法に加え、健康保険証廃止後の制度のポイントをまとめた資料も掲載されています。
マイナ保険証で受診する時は、医療機関等の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認が行われますが、資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
このような場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口に提出することで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。 協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による情報連携の開始に伴い、日本年金機構及び住民基本台帳ネットワークより加入者のマイナンバーを収集し、現在、9割以上の加入者のマイナンバーを保有しています。
しかし、窓口での事故等を防ぐために、まず健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出ることが義務付けられています。
マイナンバーを保有していない加入者の個人番号を登録するため、事業主宛に、「個人番号(マイナンバー)の提出にご協力ください」の案内が送付されています。
加えて、令和6年9月以降、協会けんぽのすべての加入者が安心してマイナ保険証を利用できるように、誤登録の確認のために、加入者の健康保険の記号番号等の資格情報とマイナンバーの下4桁を印字した「資格情報のお知らせ及び加入者情報」を事業主経由で送付することが予定されています。
【送付対象者】加入者全員
※健康保険法第3条第2項に規定される日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く
【送付時期】データ抽出を行う都合上、加入時期に応じて2回に分けて発送します
1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)
※令和6年6月7日(金)時点の加入者
2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)
※令和6年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
【送付方法】個人別に封入し、会社(事業主)経由での送付
※封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付します。
協会けんぽのHPより
また、一部の加入者分及び任意継続加入者分は被保険者分と被扶養者分をまとめて被保険者住所に送付します。
既に医療保険のデータベースに登録されている情報と住民基本台帳に登録されている情報と比較し、不一致がある方については「医療保険に関する登録データ確認のお願い」が送付されているので、必要事項保記入して提出します。
このように、協会けんぽの広報活動等が進められていますが、健康保険組合の取り扱いに関しては、所属の健康保険組合に問い合わせます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.6.5UP
毎年6月初旬に、日本年金機構から受給者あてに、「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となった「統合通知書」が送付されます。また、一定の条件を満たす方には、「支援給付金の通知」も一体となった通知書が送付されます。
年金額は毎年、法律の規定により物価・賃金の変動に応じて改定され、令和6年度は、基本2.7%のプラスとなりました。その改定後の4月分の年金が6月に振り込まれるため、6月初旬に「年金額改定通知書」が送付されます。同時に、原則年1回(定時)6月から翌年4月までの毎回振り込まれる金額が「年金振込通知書」で通知されます。
ただし、介護保険料などが特別徴収されて振込額に変更があった時や受取り口座を変更した時(随時)にも「年金振込通知書」が送付されます。特別徴収されるものとして、介護保険料額、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、個人住民税額があります。「年金振込通知書」の8月以降の控除額は、6月の額が予定額として記載されているため、詳しい控除金額などについては住所地の市区町村に問い合わせます。
また、所得税額および復興特別所得税額の特別徴収は、年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が天引きされています。
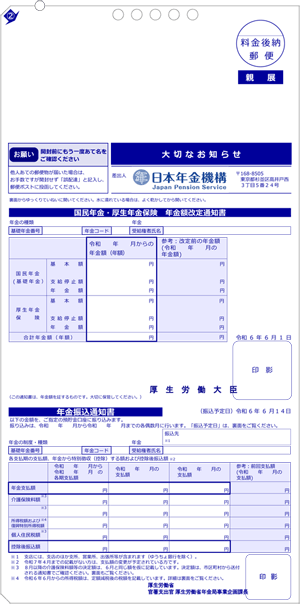
統合通知の見本(日本年金機構のホームページより)
今年は定額減税が行われるため、老齢年金および退職を事由とする年金の受給者から源泉徴収する所得税が減税されます。1人30,000円の減税額は、昨年提出した「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されます。所得税は、令和6年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を控除しきれない場合は、6月以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。個人住民税は、令和6年10月に受け取る年金から控除が行われ、10月に全額を控除しきれない場合は、以後、令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。今年は、所得税や住民税の控除額が変わるたびに「振込通知書」が送付される受給者がいます。
ちなみに、定額減税の結果、実際に所得税額から控除した減税額及び控除しきれなかった金額等については、令和7年1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票の摘要欄」に記載されます。
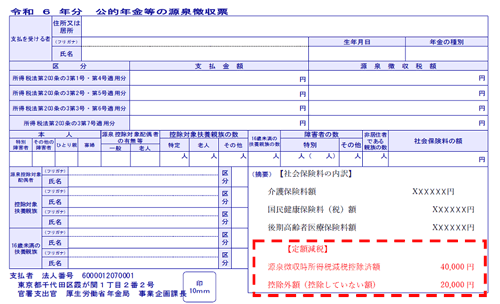
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(日本年金機構のホームページより)
最後に、老齢年金の場合は、「源泉徴収票」が交付されますが、遺族年金や障害年金は、非課税のため源泉徴収票が送付されません。「改定通知書や振込通知書」は基本、年金額の証明にはなりませんが、被扶養者の認定の際など、年金額の証明として使用可能な場合もあります。詳細は、提出先の協会けんぽや健保組合等に確認してください。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.5.7UP
健康保険証の廃止
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証を一体化し、現行の保険証の新規発行が停止され、廃止となります。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、(途中有効期間があればそこまで)従来通り使用できるよう経過措置が設けられています。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない場合については、保険者から「資格確認書」が交付され、医療機関等を受診することになります。
厚生労働省のホームページで公表されている今後のスケジュール等では、令和6年10月以降、実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)と保険者が定期的に対象者情報を連携し、保険者は対象者の申請によらず「資格確認書」を発行する予定となっています。
マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応
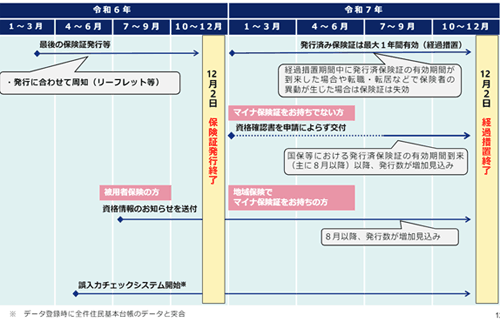
マイナ保険証と資格確認書
デジタル庁のホームページでは
- マイナンバーカードの保有者(9,168万人,全人口の73.1% 令和6年1月末時点)
- マイナ保険証の登録者 (7,143万人,カード保有者の77.9% 令和6年1月28日時点)
- マイナンバーカードの携行者
- マイナ保険証の利用経験(令和6年2月調査)(約4人に1人が利用経験あり)
令和6年2月のマイナ保険証の利用実績は、838万件、4.99%とあります。
デジタル庁ホームページより マイナ保険証の令和6年2月利用実績
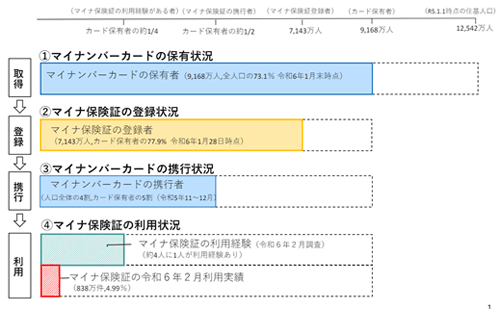
「資格確認書」の発行の対象者となる方とは
A マイナンバーカードを取得していない方 (1以外の方)
健康保険証の利用登録をしていない方 (2以外の方)
B マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
C 電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
Aについては、先ず市区町村での スマートフォン、パソコン、証明写真機、郵便などによりマイナンバーカードの交付申請が必要です。マイナンバーカードが交付されたらスマートフォン、パソコン、セブン銀行ATMなどから、健康保険証の利用を登録します。手続きが困難と思われる長期入院者や施設に入所している高齢者及び子供などは、代理人による手続きも認められています。
マイナンバーカードの健康保険証等の利用登録が完了している場合は、転職や退職、変更に伴う、再度の登録は必要ありませんが、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険の加入者は自治体)への加入の届出は、引き続き必要です。
健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した「資格取得届」「被扶養者異動届」を保険者に届け出る義務があります。
ただし念のため、初めてマイナ保険証を利用する時や転職等により新しい保険証が交付された時などは、医療機関の窓口で確認が取れない場合も想定して、マイナンバーカードと併せて保険証を持参して受診するようお勧めします。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.4.1UP
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年分の所得税額の特別控除(以下定額減税)が令和6年6月1日から実施されることとなります。定額減税の対象者は、居住者である本人と同一生計の配偶者及び扶養親族で、減額は、所得税額で3万円、住民税額で1万円の計4万円の定額です。
所得税 定額3万円の減税
(1)給与所得者の場合
令和6年分所得税の定額減税の対象者は、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入が2,000万円以下)の方です。
令和6年6月1日以後、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から最初に支払われる給与等(賞与を含む)に限る。)から源泉徴収される所得税等から定額減税額に相当する金額が控除されます。一度で控除しきれない場合は、令和6年中に支払われる給与等から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の扶養親族等の変更により、控除の額が異動する場合は、年末調整で調整することとなります。
(2)事業所得者等の場合
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
(3)公的年金等の受給者の場合
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等から源泉徴収される 所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。一度で控除しきれない場合は、令和6年中に支払われる公的年金等から順次控除されます。なお、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等は除かれます。
所得税の定額減税に関する情報は、国税庁ホームページに随時掲載されます。
住民税 定額1万円の減税
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税1万円が減税されます。減税はすべての税額控除、寄附金税額控除や住宅ローン控除などが行われた後の所得割額から行われます。
(1)給与からの特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収され、100円未満の端数は、最初の月で徴収されます。 「徴収税額の決定・変更通知書」が、全員に送付されるので確認します。
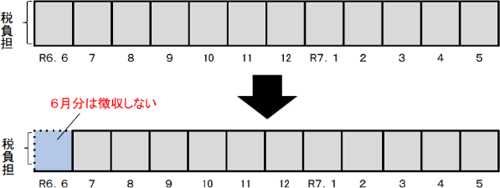
(2)普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税されます。
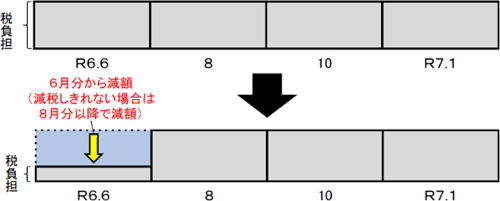 c
c
(3)年金からの特別徴収の場合
令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税されます。
なお、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税されます。
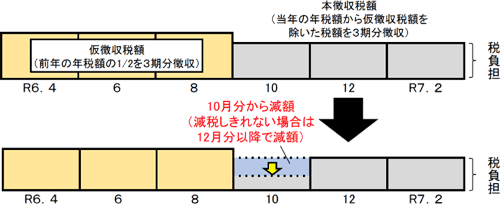
詳細は、お住いの市区町村の個人住民税の担当課に問い合わせます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.3.7UP
労災保険料率
水力発電関連の建設業などで労働者の事故率が低下していることを反映して、令和6年4月から17業種で保険料率が引き下げられ、全業種の平均は0.01ポイント低下の0.44%となります。労災保険料率は通常なら3年ごとに改定されますが、前回は新型コロナウイルスの影響を踏まえて見送られたため、今回は6年ぶりの改定となります。
厚生年金保険料率
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき、平成16年から段階的に引き上げられ平成29年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。
健康保険料率及び介護保険料率
●全国健康保険協会(協会けんぽ)
令和6年3月分(4月納付分)から適用される都道府県別の保険料率が決定されました。なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分(4月納付分)から変更となります。
協会けんぽでは都道府県ごとに健康保険の一般保険料率(特定保険料率+基本保険料率)が異なります。さらに、40歳以上65歳未満の方は介護保険料が上乗せされます。
特定保険料率とは
特定保険料とは前期高齢者納付金、後期高齢者支援金など高齢者医療制度に充てるための保険料です。特定保険料率は都道府県ごとではなく全国で一律に毎年3月に見直され、令和6年は3.42%となります。
基本保険料率とは
基本保険料率とは協会けんぽの加入者に対する医療給付や保険事業等に充てるための保険料率です。これは都道府県ごとに異なる設定がされています。最も基本保険料率が高い佐賀(10.42%)と最も低い新潟(9.35%)の差は1.07%ですが、令和5年度の1.18%から差は縮小されました。
協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されています。この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の健康作りに関する取組み(特定健診の実施率、特定保健指導の実施率、後発医薬品の使用割合等)に応じて、都道府県支部ごとの翌々年度の保険料率に反映されます。
介護保険料率とは
介護保険料率は、一律1.60%(令和5年度は1.82%)とされ、40歳以上64歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)に加算されます。
●健康保険組合
協会けんぽと同様に一般保険料は、保健、福祉事業等に使われる「基本保険料」と高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」の合計です。40歳以上65歳未満の被保険者も同じく「介護保険料」も徴収されます。さらに、健保組合間の高額医療費の共同負担事業等に使われる「調整保険料」が加算されます。
一般保険料率は3~13%の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができ、その多くは10%より低く設定されています。事業主と被保険者の保険料負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源に充てるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率の0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。詳細は、各健康保険組合に問い合わせます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.2.1UP
総務省から、1月 19 日に「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。 これを踏まえ、令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和5年度から 2.7% の引上げとなります。増額となりますが、物価変動率が、3.2%引き上げなので、実質的には目減りともいえます。
| 生年月日 | 令和5年度月額 | 令和6年度月額 | |
|---|---|---|---|
| 国民年金 老齢基礎年金(満額1人分) |
S31.4.2以後 | 66,250円 | 68,000円 (+1,750円) |
| S31.4.1以前 | 66,050円 | 67,808 円 (+1,758円) |
|
| 厚生年金 夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額※ |
224,482円 | 230,483円 (+6,001円) |
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
【年金額の改定ルール】
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和6年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて改定されます。さらに、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)も行われることによって、令和6年度の年金額の改定率は、2.7%となります。
■参考:令和6年度の参考指標
・物価変動率 :3.2%
・名目手取り賃金変動率 1 :3.1%
「名目手取り賃金変動率」とは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と3年度前の可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたものです。
名目手取り賃金変動率(3.1%) = 実質賃金変動率(▲0.1%)(令和2~4年度の平均)+ 物価変動率(3.2%)(令和5年の値)+ 可処分所得割合変化率(0.0%)(令和3年度の値)
・ マクロ経済スライドによるスライド調整率 ▲0.4%
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、 スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するもので、この仕組みは、平成16年の年金制度改正により導入されました。 マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
◆マクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.4%)
= 公的年金被保険者総数の変動率(▲0.1%)(令和2~4年度の平均) + 平均余命の伸び率(▲0.3%)(定率)
【在職老齢年金について】
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。 支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和6年度の支給停止調整額は次の通りとなります。 これにより、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の停止額が変更となり、6月の振込年金額が変わる場合があります。
| 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 48万円 | 50万円 |
なお、 物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている特別障害給付金や年金生活者支援給付金などは、 令和5年の物価変動率(3.2%)に基づき、3.2%の引上げとなります。
厚生労働省 ホームページより
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2024.1.5UP
2024年4月1日の改正
●労働条件通知書の明示内容の変更
労働基準法施行規則の改正により、全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に交付する労働条件通知書に就業場所と業務の変更の範囲を明示するよう義務付けされます。また、有期労働契約の締結と契約更新時ごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数)と内容の明示及び無期転換申込権が発生する更新時ごとに、無期転換を申し込むことができる旨など無期転換後の労働条件の記載も義務付けられます。
●裁量労働制(みなし労働時間)制度の見直し
専門業務型裁量労働制とは、業務の進め方、時間配分を労働者の裁量にまかせる制度で、現在は弁護士や税理士など19の専門業務が適用されています。これに銀行または証券会社による顧客の合併および買収に関する調査、分析、助言業務(M&A業務)が追加されます。また、労使協定等への記載事項に、労働者本人の同意を得ること、労働者が同意をしなかった場合の不利益な取り扱いの禁止及び同意の撤回の手続きを追加する義務が生じます。
●36協定(時間外労働)の猶予期間の終了
2019年4月の労働基準法改正で、36協定による残業時間の上限が原則、月45時間、年間360時間となりましたが、自動車運転の業務は、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、5年の猶予期間がありました。2024年4月1日からは、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保など「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)が適用されます。
2024年10月1日の改正
●短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
現在は、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所(特定事業所)等で、週20時間以上で勤務し、賃金の月額が8.8万円以上などの条件を満たす短時間労働者が、厚生年金保険・健康保険の加入対象となっています。2024年10月1日以降は、その特定適用事業所の対象が、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上の)事業所に拡大されます。
その他予定されている改正
●マイナンバーカードと健康保険証が一体化
他人の情報の誤登録やシステムの不具合といったトラブルが報告されていますが、2024年秋を目途に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証を一体化すると閣議決定されました。ただ、マイナンバーカードを取得しない方には、「資格確認書」を交付し、医療機関を受診できる対応などが検討されています。
●高年齢雇用継続給付金の縮小
高年齢者就業確保措置が施行されるなど高年齢者が働きやすい社会になっているため、2025年4月から、高年齢雇用継続給付金額が15%から10%へ縮小することが決定されています。
厚生労働省 ホームページより
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.12.1UP
障害年金業務統計
日本年金機構のホームページに令和4年度の「障害年金業務統計」が公表されました。
障害厚生年金、障害基礎年金の新規裁定の件数とその割合や診断書種類別の支給件数及び決定割合などがまとめられています。
令和4年度の新規裁定では、障害基礎年金・障害厚生年金の決定件数の中では2級決定が1番多く、80,008件/129,285件で61.9%、同様に、障害基礎年金の決定件数も、2級が1番多く、61,073件/81,696件で74.8%を占めています。障害厚生年金の3級は21,652件/47,589件で45.5%を占めています。
新規裁定の支給件数の診断書種類別も公表されていて、障害基礎年金では精神、知的障害が79.8%、で8割近くを占めていて、障害基礎年金・障害厚生年金の合計でも精神、知的障害が66.8%、障害厚生年金は、45.7%を占めています。
この業務統計では、他にも都道府県別の支給決定割合も公表されています。地域によって多少の差があるものの、新規裁定の障害基礎年金は、ほぼ80%台~90%台で9割前後が支給決定されています。一方、障害厚生年金の支給決定も90%台となっています。
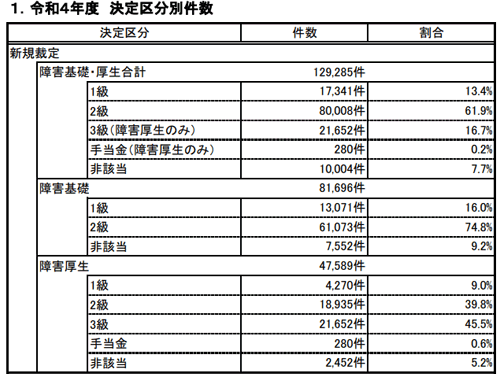
詳細は年金機構のホームページをご覧ください。
障害年金の制度
障害年金は、初診日要件、保険料納付要件及び障害状態などの条件を満たした時に受給できます。
障害基礎年金は、初診日において国民年金の被保険者期間または被保険者の資格喪失後60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日のある場合に受給できます。また、20歳前に初診日がある場合も、障害基礎年金となりますが、所得制限があります。
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、1級~3級の障害の状態にある場合に受給できます。1級または2級の障害状態であれば、障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受給でき、対象者がいれば、配偶者の加給年金と子の加算も受けられます。また障害厚生年金には、3級と障害手当金(一時金)があります。
このように、障害の原因となった傷病の初診日に加入していた制度が国民年金か厚生年金かで受給できる年金が決まり、同じ病気であっても受給額の違いや受給自体できない場合があるという様々な弊害が出ています。
例えば、長期間、厚生年金に加入していても、退職直後の国民年金期間中にケガや傷病の初診日があれば、障害基礎年金となります。仮に、同じ病気で2級に認定されたとしても、障害基礎年金であれば、(795,000円(令和5年度)だけとなり、障害厚生年金であればその上乗せの報酬比例額も受給できます。このような弊害について「社会保障審議会年金部会」において議論がなされています。
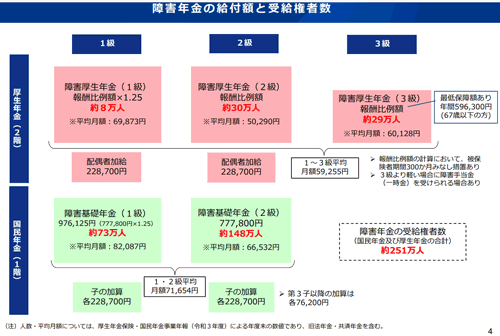
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.11.1UP
2023.年10月20日、年金機構のホームページに「社会保険適用促進手当に関するQ&A」が掲載され、具体的な取り扱いが示されました。
「社会保険料負担が発生すると手取り収入が減少する」という理由から就業調整を行う方が多数いる、いわゆる年収の壁への時限的な対応策として、社会保険適用で発生する本人の社会保険料負担相当額を上限として、事業主が「社会保険適用促進手当」を支給でき、その手当額は、保険料の算定額に算入しないという臨時かつ特例的に取り扱いができることになりました。
その対象は、新たに社会保険の適用となった標準報酬月額が10.4万円以下の方です。標準報酬月額11.0万円以上の方については、年収が128万円以上となり、社会保険の保険料負担を考慮してもなお、手取り収入が既に「106万円の壁」を越えているため対象になりません。一方、同一事業所内の労働者間の公平性を考慮し、標準報酬月額が10.4万円以下で働く既社会保険加入者については、対象となります。
令和5年10月以降、事業主から支給された「社会保険適用促進手当」は、それぞれの労働者について最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の保険料算定において除外されます。これにより、社会保険に加入したことによる減収となる保険料相当分が事業主から支給されるため、原則、本人の手取り収入が変わらないことになります。標準報酬月額が10.4万円で社会保険に加入した場合、本人負担分の厚生年金保険料が19,032円、健康保険料が5,200円(協会けんぽ 東京都介護保険料該当なし10.00%) となり、合計24,232円が本人の給与から控除されます。しかし、その分を事業主が「社会保険適用促進手当」として支給すれば、本人の手取り収入は確保され、標準報酬月額の算定にあたって、その手当金額分は除外され10.4万円のままです。
なお、2年間の判断に当たっては、保険料負担を軽減した月が基準となり、原則、「社会保険適用促進手当」による保険料負担軽減の最初の対象月から2年間が期間の上限となります。2年が経過した後は、通常の手当と同様に標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて保険料が計算されることになります。
手当の支給方法については、毎月払いか賞与時払いか等、事業所や労働者毎に異なり、就業規則や賃金規程の変更を労働基準監督署へ届出る必要もあり、詳細は労働基準監督署に確認します。
最後に、「社会保険適用促進手当」は、国が支給するものではありません。キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース等)が受けられる場合もありますが、手当を支給するか否かは、事業主の判断に寄ります。また、この算定から除外する対応策は、厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額等の決定のみです。収入が増加したことによる所得税や住民税等の取り扱いは変わらないので、詳細は、税務署や市区町村等に問い合わせます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.10.6UP
パート等で働く人がいわゆる106万円と130万円の壁を意識して収入を抑えるため、就業調整をしているケースが多い現状の対応として、政府は、9月27日に「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。厚生労働省では、10月1日から雇用保険のキャリアアップ助成金の拡充と健康保険の被扶養者の認定基準の見直しにより、壁を気にせず働ける環境づくりの後押しが実施されています。
ただし、この「年収の壁・支援強化パッケージ」はあくまでも、当面の対策としての時限措置です。以前から、自営業者の配偶者など自ら保険料を支払う人との公平性に欠くとした指摘もあることから、2025年の年金制度改正に向け抜本的な見直しが検討されています。
詳細な事務手続きについては、順次示されると思いますし、税金については、一切触れていないため今後の動向に注視していく必要があります。
(1)106万円の壁には、事業所に助成金を支給
従業員101人以上の事業所で扶養家族のまま働く人が、社会保険の適用基準を満たさないように調整する「106万円(88,000円×12)の壁」対策として、労働者の手取りが減らないように、賃上げに取り組み実質的に保険料を肩代わりする事業所は、キャリアアップ助成金「社会保険適用処遇改善コース」を受けられます。労働者1人あたり最長3年間、最大50万円受けられます。
また、社会保険適用に伴い、事業主がその被保険者の手取り収入が減らないよう、保険料負担分を給与、賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できます。この手当金は、被保険者本人負担分の保険料相当額を上限として最大2年間、社会保険料の算定対象となりません。
(2)130万円の壁一時的増収は扶養の継続
60歳未満の配偶者(認定基準額130万円未満)が、収入オーバーで配偶者の扶養を外れ社会保険に加入しない場合は、自らが国民健康保険への加入し国民年金第1号被保険者となり保険料納付の義務を負います。そのため、扶養の範囲内で収まるように年収を調整する「130万円の壁」対策として、一時的な増収であれば、直ちに扶養認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書や賃金台帳等から総合的に将来収入を判断し、事業主が「一時的な増収である旨の証明書」を添付し、加入している健康保険組合等が認めれば、連続2年まで被扶養者に留まれることになりました。
(3)配偶者手当
事業所から支給される配偶者手当についても、給与規定により限度額が定められている場合が多いため、就労時間の抑制の要因とされていると考えられ、廃止や縮小に向けた見直し(フローチャート等作成)を促すとしています。
参考:厚生労働省ホームページ
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.9.11UP
令和5年8月、厚生労働省より、「令和5年度の地域別最低賃金の改定額」が公表されました。 これは、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
1 令和5年度 地方最低賃金審議会の答申
答申では、47都道府県で、39円~47円の引上げとなり、全国加重平均額は、昨年度から43円引上げの1,004円となっています。最高額(東京都 1,113円)に対する最低額(岩手893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)となっていて、9年連続で改善されています。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会で、地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
詳しくは、厚生労働省HP及び最低賃金に関する特設サイトに掲載されています。
2 賃金の計算 (時間給で比較)方法
●日給制の計算式
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
1日の所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間です。
●月給制の計算式
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額
月給は、職務手当などの各種手当は含めますが、通勤手当、時間外手当などは除かれます。その月給を年間所定労働日数から算出した1か月の平均所定労働時間で割った時給を比較します。
最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効であり、差額分の支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。
3 最低賃金の減額の特例許可制度
「最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」もあります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。
使用者が都道府県の労働局長に申請を行い、許可を受けること(最長3年)でその労働者については最低賃金の適用がされません。(最低賃金法7条)
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.9.11UP
2022年10月から厚生労働省の社会保障審議会(年金部会)で、次期年金制度改正へ向けた議論が始まっています。厚生労働省のホームページに掲載されている主な意見の一部をみていきます。
なお、公的年金制度では、5年ごとに「財政検証」が実施されていて、2024年夏以降に公表される「財政検証のオプション試算」等を踏まえて、改正法案が提出される見込みです。
社会保障審議会(年金部会)でのご意見より一部抜粋
(1)総論的な事項
●公的年金の役割
年金制度は、目の前の問題に対応しながらも、先を予測しながら改革していく必要がある。効果が出るまでに大変時間がかかるため、ある程度先読みをしながら、給付の十分性と財政の持続可能性の担保をしていかなければいけない。公的年金は高齢者世帯の収入の6割以上を占めており、老後の生活の柱となっているため、あるべき公的年金制度を検討するに当たっては、給付の十分性を確保する視点が求められる。
●公的年金と私的年金の連携
私的年金は企業年金・個人年金部会で検討されているが、公的年金と私的年金の役割分担や連携、高齢期の所得保障の全体を一体として考えていく視点を持つべき。
(2)現役期と年金制度の関わり
●被用者保険の適用拡大 (勤労者皆保険)
全ての労働者への社会保険の完全適用に向けて、前向きな議論を行うべき。
どのような働き方をしてもセーフティネットが確保され、誰もが安心して働けることが重要である。(令和5年4月以降101人以上の事業所が令和6年 10月からは51人以上の事業所まで拡大されます。)
●子育て支援
年金制度の議論は人口推計に連動して行うので、少子化への対策として子育支援のさらなる充実と推進が必要
●障害年金
厚生年金保険料を一定期間納めていれば、保険事故の発生が厚生年金の被保険者期間中に存在しなくても、退職後それほど期間が経過していなければ、障害厚生年金の給付の対象にすることも検討の余地があるのではないか。
(3)家族と年金制度の関わり
●遺族年金
共働き世帯の増加等現代の状況に応じた給付。男女間の差の是正
●女性の就労の制約と指摘される制度等(いわゆる年金の壁)や第3号被保険者制度
被扶養者の認定基準130万円(60歳以上だと180万円)を超えないよう調整してしまう。
ただし、被用者保険に加入して負担する社会保険料は、決して働き損ではなく、それに見合う給付を受けられるものであることを丁寧に国民に説明していくことが必要。他方、被用者保険に加入せずに、年収が130万円を超えて、第3号被保険者から第1号被保険者に変わる際は、保険料が増えても給付は増えないため、いわば働き損になっている。
(4)その他の高齢期と年金制度の関わり
●高齢期の働き方(在職老齢年金制度)
就労の長期化を年金制度に反映することにより、長期化する老後生活の経済基盤の充実が図られるよう、 今後の高齢期の就労の変化を念頭に、高齢期の就労と年金の在り方について検討を進めていくことが求められる。高齢者雇用においては、より多様な形での就業機会の確保が進められる中、就労と年金の組合せの選択がより多様で柔軟にできるよう、引き続き検討を続けるべき。
●基礎年金の拠出期間延長
保険料納付期間を現行の「20歳から60歳までの40年間」から「65歳になるまでの45年間」に延長する案
●マクロ経済スライドの調整期間の一致
マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、国民年金と厚生年金で別々に行われる仕組みで、積み立金も別となっていて財政が均衡するまで調整が続けられます。厚生年金と国民年金の間で財政調整を行い、マクロ経済スライドの終了時期を一致させることで、基礎年金の水準改善を図る。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.8.1UP
遺族年金制度は、家計を支える方が死亡した場合に、残された遺族の所得保障を行うことが目的ですが、現行法では、依然として、主たる家計の担い手である「夫」が死亡し、残された妻と子※の生活を保障するという考え方を内包した給付設計となっています。
※子、孫とは、18歳到達年度の末日までにある子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子を指します。
国民年金独自の給付である寡婦年金は、婚姻期間が10年以上ある死亡した夫に生計を維持されていた等の要件を満たす「妻」にのみ、60歳から65歳の間支給されます。
また、遺族基礎年金は、「子または子のある配偶者」の生活の安定を図ることを目的とされていますが、以前はその対象が、 「子のある妻」だけでした。平成26年4月「子のある配偶者」と、夫も対象遺族となるよう改正されました。
遺族厚生年金の対象者は、死亡した方に生計を維持されていた次の遺族です。
- 子のある妻、または子(遺族基礎年金を受給できる遺族)
- 子のない妻 。夫の死亡時に30歳未満で子のない妻への遺族年金の給付は、5年間の有期給付となります。
- 孫※
- 55歳以上の夫、父母、祖父母で、支給開始は60歳からとなります。ただし 遺族基礎年金の支給対象となっている夫の遺族厚生年金は、60歳前でも支給されます。
対象遺族の年齢について、夫は55歳以上ですが、原則、妻には年齢制限がありません。
さらに、遺族厚生年金には、就労が困難であろう次に該当する65歳未満の「妻」には、中高齢の寡婦加算が支給されます。
- 夫の死亡時に40歳以上(長期要件により受給する場合、夫の厚生年金被保険者期間が240月以上)で子のない妻
- 40歳時点で遺族基礎年金の受給権を有する子があったが、子が18歳到達年度の末日に達した(1級・ 2級の障害の状態にある子が20歳に達した)等の理由で、遺族基礎年金の受給権を失った妻
また、昭和31年4月1日以前に生まれた妻には、65歳以降も、経過的寡婦加算が支給されます。
実際、夫が特別支給の老齢厚生年金の受給者である場合、65歳前は1人1年金の原則により、遺族年金との選択となり、在職等で老齢年金が全額停止であれば、遺族年金を選択するケースが見られます。しかし、65歳以降は、自身の老齢厚生年金額の方が高くなり、遺族厚生年金が支給されない (先あて)ケースが多い現状です。
このように「妻」だけの給付や加算が行われている現行法を、現代の社会情勢に合わせて、共働きが一般化することを前提とした遺族年金制度の在り方、制度上の男女差の解消や養育する子がいない家庭における有期化又は廃止を含めての検討がされています。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.7.4UP
令和5年6月12日に厚生労働省から「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について」という事務連絡が発出されました。この通知は、平成30年7月に示された事務連絡の内容を変更するのではなく、諸手当等が、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」又は「賞与」のいずれに該当するのかを明確化したものです。具体的には、
- 諸手当等の名称の如何に関わらず、諸規定又は賃金台帳等から、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること
- 賞与に係る諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与に係る報酬」に該当せず、「賞与」として取り扱うものであること
とされました。
そもそも、「通常の報酬」とは、毎年7月1日現在における賃金、給与、俸給、手当等で毎月支給されるものです。「賞与」とは、給与と別に労働の対償として支給される「通常の報酬」以外のもので、支給回数が年3回以下のものです。一方「賞与に係る報酬」とは、諸規定によって年4回以上の支給があると客観的に定められているものです。手続き上は、「賞与」は、賞与支払い時に「支払い届」を提出しますが、「賞与に係る報酬」は標準報酬月額の定時決定等に含んで届出ます。
「賞与」と「賞与に係る報酬」とでは社会保険料額が変わります。「賞与」の保険料は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額に健康保険料率と厚生年金保険料率を掛けた額となります。健康保険の標準賞与額の上限は、毎年4月から翌年3月までの年度計で573万円です。また、40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料も納付します。厚生年金保険料は、標準賞与額の上限が年度計ではなく「1カ月あたり150万円」です。
「賞与に係る報酬」は、標準報酬月額の定時決定等の際に通常の報酬に加算します。例えば、年間で36万円の手当が「賞与」の時の保険料は、次の式で計算されます。(事業主と折半しない料率)
36万円×(健康保険料の料率11.82%*+厚生年金保険料率18.300%)
※11.82%は、令和5年3月から 東京都の介護保険第2号被保険者に該当する場合の料率
「賞与に係る報酬」であれば、7月1日前の1年間に受けた額を、12ヵ月で割った1ヶ月当りの金額、こり場合は3万円を通常の報酬に加算して、定時決定等で届けます。等級によっては、標準報酬月額が変わらない場合もありえます。
このように、納付する保険料額も異なりますが、傷病手当金等の保険給付額や将来の年金の給付の額にも影響します。
先の事務連絡のQ&AのQ.3で「同一の性質を有すると認められるもの毎に判別する」質問に対して、業績に応じて支給される手当を例に、給与規程及び賃金台帳上の扱いや客観的な区分がされているかどうかで「賞与」と、「賞与に係る報酬」についての3事例が示されています。またQ.7では、支給回数について説明されているので、詳しくは、次の資料をご参照ください。
通知「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について
日本年金機構ホームページより
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.6.1UP
令和5年3月から健康保険料と介護保険料が改定され、変更後の保険料は、4月の給与から源泉控除されていることでしょう。また、6月の給与からは、令和5年度の個人住民税の特別徴収が始まるため、住民税が昨年よりも多い方の手取り(給与の振込額)が減る場合もあるでしょう。給与から控除される税金額は、給与明細や市区町村から「特別徴収税額決定通知」等で確認できます。住民税額等の詳細については、住所地の市区町村に問い合わせます。
特別徴収は、従業員が納付すべき住民税を勤務先である事業者が毎月の給与から控除し、本人の代わりに納付する方法です。地方税法により、所得税の源泉徴収義務のある事業者には、住民税を特別徴収して納付することが義務付けられています。
健康保険料
全国健康保険協会での保険料率は、都道府県ごとの年齢構成や所得の水準により調整されます。令和5年3月からは、13都府県(栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、福岡) の保険料率が上がり、静岡が変更なし、その他33道県の保険料率は下がりました。
令和5年4月より、保険料率の伸びを抑制する取り組みとして、生活習慣病予防健診等の自己負担額が、従来の7,169円から総合健保組合の水準を参考に5,282円 に軽減されました。これは、予防健診の受診を推進し病気の早期発見につながれば医療費が削減でき、保険料率の伸びが抑制できるという対策です。
介護保険料
40歳から64歳までの健康保険加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。令和5年3月から、介護保険料率は、全国一律に「16.4/1000」から「18.2/1000」と0.18%、引き上げられました。
一方、65歳以上の老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金受給者で、年間の受給額が18万円以上の場合、年金から介護保険料が天引き(特別徴収)されます。ただし、老齢基礎年金を受給せず(繰下げ待機)、老齢厚生年金のみ受給している場合は、特別徴収の対象とはならず、市区町村から送付される納付書で納めることになります(普通徴収)。
雇用保険料の改定
雇用保険からは失業や育児・介護などで収入が減少した時に労働者の生活を守るための給付が受けられますが、新型コロナウイルスの感染拡大によって休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」及び失業手当の増加などから財源不足が問題となりました。雇用保険料は、「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3種類の事業があり、事業の種類や事業主と労働者で負担する料率も異なります。
令和4年度は4月から事業主負担の保険料率が、10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率と2回の変更がありました。令和5年度は4月から一般の事業の労働者負担・事業主負担ともに 6/1,000に変更になり、農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更となりました。
厚生年金保険料
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられ平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
子ども・子育て拠出金率は、令和2年4月より0.36%ですが、こちらは全額事業主負担となります。
最後に
異次元の子育て支援対策の1つである「児童手当の拡充」等の財源として、消費税などの増税ではなく、1ヶ月あたり500円程度を医療保険料へ上乗せすることにより確保する案が検討されています。(令和5年5月末時点)
(参考)厚生労働省、日本年金機構、全国健康保険協会等のホームページ参照
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.5.1UP
マイナンバーカードを健康保険証として利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、「セキュリティ面で不安」という声もありますが、2023年4.月9日時点で利用登録件数は、57,086,000件となっています。
令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてオンライン資格確認のシステム導入(顔認証付きカードリーダー設置)が、原則義務づけられており、順次導入が進められています。
顔認証付きカードリーダーとは、マイナンバーカードを保険証として利用するのに必要な機器で、マイナンバーカードの顔写真データを IC チップから読み取り、その「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」と照合、または暗証番号で本人確認が行われます。
本人確認ができれば、薬の履歴や特定検診の結果などの情報を受けられます。マイナンバーカードのICチップ部分には、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されません。 健康保険証として利用しても、特定健診結果や薬剤情報がICチップに記録されることはないと説明されています。
4つのメリット
(1)薬の履歴や特定検診の情報提供を受けられます
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身の薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に本人が同意すると、口頭で説明していたそれらの情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができるといわれています。
(2)限度額適用認定証等の提出が不要となります
「限度額適用認定証」とは窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証明ですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、 「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されるため、患者の一時的な自己負担や限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
(3)医療費控除の申請手続きに利用できます
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、確定申告の際、領収証を保管・提出する必要がなく、医療費控除申請ができます。
(4)就職・転職・引越後も健康保険証として使えます
新しい医療保険者へ手続済であれば、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は、定期的な被保険者証の更新が、また、高齢受給者証の持参が不要となります。
※医療保険者等が変わる場合の加入の手続は、引き続き必要です。
医療費負担
マイナンバーカードを健康保険証として利用して、薬剤情報などの提供について同意すれば、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、下表のとおり診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。
| 特例措置 (令和5年4~12月) |
|||
|---|---|---|---|
| 初診 | マイナンバーカードを | 利用しない | 6点 |
| 利用する | 2点 | ||
| 再診 | マイナンバーカードを | 利用しない | 2点 |
| 利用する | 2点 | ||
| 調剤 | マイナンバーカードを | 利用しない | 4点 |
| 利用する | 1点 |
(厚生労働省ホームページより)
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.3.7UP
年期額の改定
令和5年度の年金額は、額改定に用いる「賃金変動率」が2.8%のプラス、「物価変動率」が2.5%のプラスだったため額改定のルールに基づき、67歳以下の方(新規裁定者)は賃金、68歳以上の方(既裁定者)は、物価によって改定されることになりました。
ただし、現在はマクロ経済スライドによる給付水準調整の期間のため、賃金・物価から5年度のスライド調整率▲0.3%とキャリーオーバー分▲0.3%を引くこととなり5年度の改定率は、67歳以下の方(新規裁定者)は2.2%、68歳以上の方(既裁定者)は、1.9%となりました。
具体的に次の金額となります。
●令和5年4月からの年金額
| 新規裁定者 S31.4.2以降生まれ |
既裁定者 S31.4.1以前生まれ |
||
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 老齢基礎年金 | 795,000円 | 792,600円 |
| 障害基礎年金1級 | 993,750円 | 990,750円 | |
| 障害基礎年金2級 | 795,000円 | 792,600円 | |
| 遺族基礎年金額 | 795,000円 | 792,600円 | |
| 子の加算(1人につき) | 228,700円 | ||
| 子の加算(3人目以降) | 76,200円 | ||
| 老齢厚生年金 | 配偶者加給年金 | 228,700円 | |
なお、令和5年4月から改定されるので6月に振り込まれる年金額から変わります。受給者の方には、原則6月初旬に「年金額改定通知」と「振込通知」が一体となった「統合通知書」が郵送されます。
年金生活者支援給付金の改定
物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されているため、令和4年の物価変動率(2.5%)に基づき、年金生活者支援給付金は、2.5%の引き上げとなります。
生活者支援給付金額
| 老齢年金 | 5,140円(*基準額) |
| 障害年金1級 | 6,425円 |
| 障害年金2級 | 5,140円 |
| 遺族年金 | 5,140円 |
*老齢年金の保険料納付済み期間に基づく給付月額は、「5,140円(基準額)×保険料納付済み期間/480月」で計算されます。
在職老齢年金について
在職老齢年金は、総報酬月額相当額(賞与込みの月収)と年金の基本月額の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、平成16年度の48万円に平成17年度以降の各年度の名目賃金変動率を乗じて1万円単位で改定されます。令和5年度の支給停止調整額は 48 万円となります。
国民年金保険料について
国民年金の保険料は、平成 16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成 29 年度に上限(平成 16 年度水準で 16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。
その上で、平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度水準で、保険料が月額100 円引き上がり17,000 円となりました。
実際の保険料額は、平成16 年度水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和6年度の保険料額は次の通りとなります。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 法律に規定された保険料額 平成16年度水準 |
17,000円 | 17,000円 | 実際の保険料額 | 16,520円 | 16,980円 |
|---|
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.2.1UP
総務省から、「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたのを踏まえ、令和5年1月20 日、厚生労働省から令和5年度の年金額が公表されました。法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は令和4年度から 2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から 1.9%の引き上げとなります。
年金額の改定ルール
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。 このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されます。 また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分(キャリーオーバー)による調整(▲0.3%)が行われるので、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となります。
令和5年度の年金額改定に係る各指標は、
- 物価変動率:2.5%
- 名目手取り賃金変動率:2.8%
- マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.3%
- 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分 :▲0.3%
「名目手取り賃金変動率」とは、 実質賃金変動率(0.3%) + 物価変動率(2.5%)+ 可処分所得割合変化率(0.0%) (令和元~3年度の平均) (令和4年の値) (令和2年度の値)です。
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、 スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から 控除するもので、この仕組みは、平成16年の年金制度改正により導入されました。 マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
「前年度までのマクロ経済スライドの未調整分」とは、 ▲0.1%(令和3年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分) + ▲0.2%(令和4年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)です。
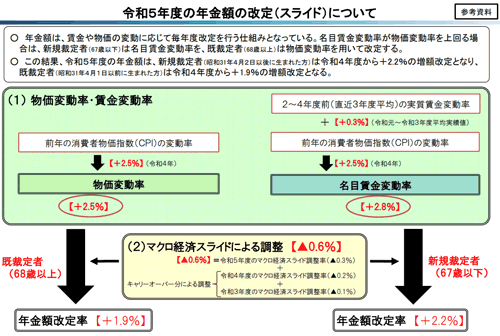
(厚生労働省 ホームページより)
令和5年度の老齢基礎年金の満額は2パターン
令和5年度の改定率で計算すると、新規裁定者(67歳以下)は「1.018」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.022)となり、令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、780,900円×1.018≒795,000円 となります。既裁定者(68 歳以上の方)は「1.015」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.019)なので、令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、780,900円×1.015≒792,600円 となり、久しぶりに、名目上の年金額は増額されました。しかし、物価上昇分(2・5%)に追い付かないので、実質的には、目減りしている感は拭えないでしょう。

(厚生労働省 ホームページより)
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2023.1.5UP
予想以上に出生率が減少する一方、人生100年時代に向け、持続可能な公的年金制度にするために高齢者や女性の就業を進め、社会保険の加入の拡大や受給方法の多様化等を盛り込んだ「年金機能強化法」が施行されています。
加入の拡大においては、短時間労働者の社会保険加入の事業所の被保険者数の総数が引き下げられ、平成28年は、501人以上でしたが、令和4年10月からは101人以上の事業所に拡大されました。
これにより、従来、健康保険の扶養家族で国民年金第3号被保険者だった方が、健康保険・厚生年金の被保険者となりました。その際、同じ収入でも保険料を負担するので手取り額は減りますが、将来の厚生年金分が増えていくことになります。また、令和6年10月には、被保険者の総数が常時51人以上の事業所に拡大され、加入者も増える見込みです。
次いで、受給方法の多様化には、年金の繰上げ受給の減額率が0.5%から0.4%となり、繰下げ受給の上限が70歳から75歳に引き上げられました。
繰上げ受給では、昭和37年4月2日以降に生まれた男性(昭和42年4月2日以降に生まれた女性)が繰上げ請求したときに、従来の0.5%から0.4%に引き下げられ、年金の繰上げ受給がしやすくなりました。そり以前に生まれた方の変更はありません。
繰下げ受給の上限は、70歳から75歳に引き上げられ、75歳まで繰り下げた場合、84%(0.7%×120月)増額されるようになりました。平均寿命が男性81.47歳、女性で87.57歳(2022年)という状況の中、老後の生活保障として増額した年金を受けられます。
しかし、10年間、年金を受給できない生活への不安や何より「いつまで生きられるか、寿命が分からない」という声が聞こえます。そんな中、令和5年4月に1日から「繰下げみなし」が始まります。これは、繰下げ請求手続きをしなかった73歳の方が健康上の理由等から繰下げせず、65歳に遡って受給したいと希望した場合、従来は、65歳から68歳の3年分が時効(5年)により消滅していました。この救済として70歳を過ぎて請求した時、5年前に繰下げ請求の申し出があったとみなして、増額した年金を受けることができるようになります。先の事例であれば、68歳時点で繰下げ申し出したとみなして、増額した年金額 (0.7%×36月)を5年分受給できるようになります。
なお、年金の繰上げ・繰下げ受給は、ご本人の収入や税金(所得税・住民税)といった経済状態や健康状態及び予測不可能な寿命など様々な要素で判断し、決定することになります。総受給額の逆転時期や他の遺族年金や障害年金との調整もあるため、一生の受給方法を決めるにあたって、年金事務所だけでなく税金(所得税・個人住民税)や保険料(介護・国民健康保険)については、該当する税務署や市区町村でご相談されることをお勧めします。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.12.9UP
被保険者等が保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)が決定した処分に不服があるときに、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に規定された資格や保険(年金)給付に関する審査請求の事件を担当しています。そして、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこれを行うこととされています。
また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料等に関する不服については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。
審査請求の手続きとしてはまず、不支給通知書に記載されている処分(決定)の理由を確認し、不明な点等詳細については、決定した保険者に問い合わせます。その説明を受けて、争点を絞ったうえで地方厚生局に審査請求書を提出します。審査請求書の用紙は、地方厚生局のホームページからダウンロードできます。また年金事務所にも備え付けてあり、受付もしてくれます。
審査請求は、口頭でもできることになっていますが、法令に定められている手順(陳述書の作成等)を踏まねばならず、筆記が困難であるなど特別な場合を除き、審査請求書の提出による手続きをお勧めします。
社会保険審査官は、審査請求書を受付けると、審査請求人に対し受付通知等を送付し、保険者に対して関係資料等の提出を求めます。その関係資料等が社会保険審査官に届いてから審査を行うこととなるため時間がかかります。そのため、障害年金の認定日での請求が不支給となり審査請求をする傍ら診断書を取り直して事後重症での新規請求を進めることも可能です。その場合、審査請求の結果により、年金が調整されます。
社会保険審査官が審査を終えると、審査請求人あてに決定書が送付されます。審査請求の決定には、容認、棄却、却下があり、棄却は審査請求が認められない場合、却下は審査請求が期限内に行われなかった場合などです。その審査請求の結果にさらに不服がある場合は、その決定書が送付された日の翌日から起算して2月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求行うことができます。 社会保険審査会は、審査長と審査委員5名の合計6名での合議制で審議が行われます。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。ただし、
- 審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
- 決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。
なお、物価スライドなどの年金制度に対する内容は審査請求の対象となりません。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.12.1UP
親が定年等により退職後、条件を満たせば、子(被保険者)の健康保険の扶養家族や税法上の扶養親族になることができます。
健康保険の被扶養者になるための条件
- 子(被保険者)に生計を維持されていること
- 親の年齢が75歳未満であること(75歳以上は後期高齢者となります)
- 60歳以上で同居の場合、年間収入が180万円未満であり、かつ、子(被保険者)の年間収入の半分未満であること
別居の場合は、年間収入が180万円未満で、かつ、子(被保険者)からの仕送り額未満であること
なお、60歳未満の場合の年間収入は130万円未満となります。 - 日本国内に住んでいること
年収には、公的年金(老齢、遺族、障害) や傷病手当金及びハローワークからの失業等給付も含まれます。
協会けんぽの被扶養者の届は、事業主を経由して日本年金機構へ提出します。健康保険組合の被扶養者の届については、加入している健康保険組合となりますので、添付書類等詳細については、年金機構や健康保険組合に問い合わせます。
税法上の扶養親族となるための条件
扶養親族となるのは、その年の12月31日の時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
- 青色申告者、白色申告者の事業専従者でないこと。
仮に、子(納税者)の課税対象所得が500万円で所得税率が20%の場合、親が70歳以上であれば48万円(同居している場合は58万円)の扶養控除が受けられます。結果、納税者と親が同居していれば、合計所得金額から58万円を控除することができ、所得税は11.6万円少なくなります。
●扶養控除が認められない場合 500万円 x 20% = 100万円
●扶養控除が認められる場合 (500万円 -58万円)x 20% = 88.4万円
また、住民税も、70歳以上であれば、課税対象額から38万円(同居している場合は45万円)の扶養控除額が受けられます。
扶養親族については、その年の12月31日の時点の判断となるので年末調整または、確定申告で申告することになります。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.11.1UP
2022年1月1日健康保険制度の改正より、任意継続被保険者が期間の途中で任意喪失できるようになりました。従来、退職時には、「任意継続の保険料」と「国民健康保険料(税)」を比較して、負担する保険料が少ない任意継続を選択していました。その方が、再就職もせず収入は、失業給付と年金しかないため所得が減り、次の年の国民年金保険料の方が安くなる場合がありました。そのため、任意継続の資格を喪失して国保に切り替えるには、任意継続の保険料を納期までに納めず、滞納による喪失というリスクの高い手段をとらざるを得ませんでした。このような状況を踏まえ、任意継続を申し出により2年経過する前に喪失できるよう改正されました。なお一度喪失申出をすると取り消しはできません。
そろそろ1月から12月の1年間の収入(所得)が決まる頃です。退職時と状況が変わるので再び「任意継続の保険料」と「国民健康保険料(税)」を比較する機会です。その際、扶養家族がいる方は、本人の保険料だけでなく世帯としての保険料の総額を考慮して選択する必要があります。任意継続では、扶養家族が何人いても保険料は被保険者1人分です。一方、国民健康保険料(税)には、扶養家族という概念はなく、世帯の所得と加入者数によって決まるので、家族の分だけ保険料が増える仕組みです。
国民健康保険料(税)の算定方法は、前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算され、同月中旬に世帯主宛てに国民健康保険料額通知書が送付されます。算定方法は、各市区町村で異なるので、住民票のある市区町村の国民健康保険の窓口で算出してもらうことをお勧めします。
国民健康保険料(税)は、基本「医療分」「後期高齢者支援分」「介護分」の3種類の合計額となります。医療分は国保加入者の医療費分、後期高齢者支援分は後期高齢者医療制度、介護分は介護保険事業の財源を確保するために徴収される保険料です。各市町村が採用している計算方法(所得割や均等割など)によって年間保険料が算出されます。介護分は40~64歳の加入者のみに課されます。
国民健康保険料(税)を確認したうえで、任意継続の喪失を申し出る時は、加入している協会けんぽや健保組合に資格喪失届を提出します。喪失日は、協会けんぽ等が申出書を受理した日の属する月の翌月1日です。4月に切り替えたいときは、3月中に協会けんぽ等に申出書を提出し、保険証の使用期限は資格喪失を申し出た3月末日となります。翌月1日以降に資格喪失証明書が送付され、任意継続被保険証等を返却します。
もし任意継続の保険料を前納しているときは、資格喪失日以降に還付されます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.10.3UP
男性の育児休業取得促進のために、子の出生直後の時期における「産後パパ育休の創設」と「育児休業の分割取得」が施行されました。
出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設
改正前は、子の出生日から8週間以内であれば取得日数に制限を設けず、一人につき1回のみ取得する「パパ休暇」として運用されていました。改正後は、「産後パパ育休」が創設され、子どもが誕生した8週間以内であれば、4週間(28日間)まで取得できるようになりました。取得する時期は、自分で選ぶことができ、事前に取得申請するのが基本で遅くても取得希望する2週間前に申し出ます。
「産後パパ育休」も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に給付の対象となります。育児休業給付については、最寄りのハローワークへ問い合わせます。
育児休業の分割取得の施行
改正前の育児休業は、1回でまとめて取得するのが基本であり分割取得ができませんでした。改正後は、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割2回で取得できるようになりました。これにより、夫婦ともに1歳までの育児休業を2回に分割して取得することができるため、仕事の繁忙期と閑散期や妻の育休復帰時期などを考えながら、夫婦が交代で育児休業を取得できるようになるでしょう。なお、夫婦が途中で交代する場合は、配偶者の育休終了日と本人の開始日が接続または重複している(切れ目がない)ことが要件となります。なお、1歳以降の育児休業については、現行通り分割取得はできません。
社会保険料の育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
2022年10月から短期間の育児休業等を取得した場合の対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されるようになりました。また、賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。社会保険料の免除申請については年金事務所に問い合わせます。
| 産後パパ育休 (R4.10.1 ~) 育休とは別に取得可能 |
育児休業制度(R4.10.1 ~) | 育児休業制度(現行) | |
|---|---|---|---|
| 対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
| 分割取得 | 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) | 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) | 原則分割不可 |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
| 1歳以降の延長 | - | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
| 1歳以降の再取得 | - | 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |
※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2 具体的な手続きの流れは以下(1)~(4)のとおりです。
(1)労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
(3)労働者が同意
(4)事業主が通知
厚生労働省ホームページより
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.9.1UP
「扶養親族等申告書」とは
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされていて、日本年金機構や共済組合等の年金支払者は、年金の支払期ごとに支給額から所得税を源泉徴収することが義務付けられています。
申告に基づき、年金額から障害者控除や配偶者控除等の各種控除を行い所得税の計算がされます。そのため、日本年金機構等から該当する受給者あてに、毎年「扶養親族等申告書」の用紙が送付されますが、その支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、この申告書が不要なので送付されません。
控除対象となるのは、年間所得見積もりが95万円以下の配偶者と48万円以下の扶養親族です。また、年金から特別徴収された介護保険料や国民健康保険料は、社会保険料として控除されます。年金以外の収入(給与等)がある方や医療費控除や生命保険料等控除を希望する時は、確定申告をする必要があります。 配偶者や扶養親族がいなくても、受給者本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当する場合も、申告書を提出することで、該当の控除が受けられます。
なお、本人、配偶者、扶養親族等いずれも該当しない場合は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。提出しなくても、所得税率は、一律5.105%(復興特別所得税を含む)で計算されます。
令和5年の税制改正
令和5年1月1日に次の2点が施行され、扶養親族申告書の様式の一部も変更されます。
(1)非居住者の扶養親族を控除対象とする場合
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げるいずれにも該当しないものが除外されます。
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てる ための支払を 38 万円以上受けているもの
(2)配偶者・扶養親族が退職所得を受ける見込みのある場合
令和5年に退職手当を受ける見込みのある配偶者・扶養親族がいる場合、翌年度の地方税の計算に反映させるため「退職所得を除いた年間所得見積もり額」を申告するように変わります。なおこの対象者は、退職所得を除いた年間所得見積もり額が、配偶者は95万円以下、扶養親族は48万円以下の方に限られます。
(参照 日本年金機構、国税庁のホームページ)
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.8.1UP
在職定時改定制度とは
従来、老齢厚生年金受給者が65歳以降厚生年金に加入したときは、資格喪失時または70歳到達時に65歳以降の被保険者期間を合算して年金額が改定されてきました。
しかし、令和4年4月からは、在職中でも就労した効果が年金額に反映するよう「在職定時改定制度」が導入されました。これは、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者で、基準日である毎年9月1日に厚生年金の被保険者であるときに、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金額から改定するものです。
令和4年については、受給者の65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間を一括して、年金額が改定され12月に振込まれます。
なお、在職定時改定は、特別支給の老齢厚生年金や65歳前の繰上げた老齢厚生年金および70歳以降の老齢厚生年金には適用されません。また、繰下げ待機中 (繰下げ受給を希望していて老齢厚生年金を受給していない状態) も在職定時改定が適用されません。
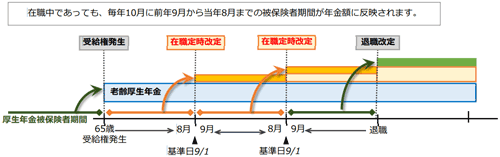
厚生労働省ホームページより
在職定時改定により加給年金と振替加算が発生するとき
65歳時点では厚生年金の加入期間が240月未満(共済組合の加入期間も含む)の老齢厚生年金受給者が、在職定時改定により240月以上となったときに、一定の要件を満たせば受給者本人には加給年金がその配偶者には振替加算が加算されます。
(1)老齢厚生年金受給者本人に加給年金が加算されるケース
- 老齢厚生年金が支給されているとき (在職老齢年金により全額停止されていない)
- 生計を維持している65歳未満の配偶者および18歳到達年度末までの子もしくは20歳未満の障害の状態のある子がいるとき
(2)老齢厚生年金受給者の配偶者に振替加算がつくケース
受給者本人が240月以上になった時に配偶者が65歳以上であると加給年金は加算されません。
しかし、配偶者が次の条件を満たせば、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。この時に、受給者本人の老齢厚生年金が全額停止(在職老齢年金により)されていても振替加算の請求は可能です。
- 生計を維持されている65歳以上の配偶者であるとき
- 配偶者の厚生年金加入期間(共済組合の加入期間も含む)が240月未満であること
一方、65歳時点では240月未満で老齢基礎年金に振替加算を受給して人が在職定時改定により240月を超えると、その時点から振替加算を受給できません。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.6.13UP
法人事業所と国・地方公共団体の事業所及び常時5名以上の従業員を雇用している個人事業所は、強制適用事業所として社会保険の加入が義務付けられています。
平成28年10月から、「特定事業所」といって事業主が同一である適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所で働くパート、アルバイトなどの短時間労働者が一定の要件を満たす場合、社会保険の被保険者となります。
短時間労働者の一定の要件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 継続して1 年以上雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと
令和4年10月から、特定適用事業所の基準となる被保険者の総数が常時100人を超える適用事業所に拡大されます。 他にも3の短時間労働者の勤務期間が、継続して「1年」が廃止され「2か月を超えて」に変わります。また、令和6年10月からは特定適用事業所の基準となる被保険者の総数が常時50人を超える適用事業所になります。
現在、60歳未満で年収を130万円未満に抑えて、配偶者の健康保険の扶養家族で国民年金第3号被保険者となっている場合でも、一定の要件を満たせば、社会保険の被保険者となります。扶養家族であれば社会保険料の負担はありませんが、被保険者となれば毎月の給与や賞与から社会保険料が(事業主と折半の金額)源泉徴収されます。
厚生労働省のモデルケースでは月収88,000 円で、毎月約8,000 円(年額約96,000円)の厚生年金保険料を40 年間納付すれば、毎月約19,300 円 (年額約231,500円)の年金がもらえると説明しています。
事業主は、被保険者でない短時間労働者(パート、アルバイト等)に対して、法律改正により社会保険加入となることの事前説明が必要となるでしょう。手厚い給付が受けられるメリットがあるものの保険料負担により手取りが減るため、今後の働き方について労働条件の見直し等の相談が増えることも予想されます。
日本年金機構のホームページに、新たに被保険者となる方への制度説明会等を行う際に、無償で社会保険労務士等の派遣を依頼できる制度の案内が出ています。詳しくは、年金機構のホームページをご参照ください。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.5.9UP
配偶者加給年金について
厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)ある方(以下老齢満了者といいます)が、65歳到達時点または定額部分支給開始年齢に到達した時点に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる時に、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)に配偶者加給年金が加算されます。
また、退職改定や70歳到達時に老齢満了者となった場合や令和4年の法律改正による「在職改定」で老齢満了者となった時も加給年金が加算されますが、この場合は、加給年金の届が必要です。
令和4年4月から加給年金の支給停止の規定の見直しについて
加給年金対象者である配偶者も老齢満了者で老齢厚生年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、加給年金額は支給停止されます。ただ、令和4年3月までは、加給年金対象者である配偶者の年金が在職老齢や失業給付を受給している等の理由により、全額支給停止となっている時は、加給年金が支給されていました。
しかし、年金制度の改正により、令和4年4月以降は、加給年金対象者である配偶者も老齢満了者で、老齢厚生年金を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により支給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額が支給停止されるようになりました。
加給年金支給の経過措置について
ただし、令和4年3月31日時点で、配偶者加給年金が支給されている次の方の場合に、引き続き配偶者加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
経過措置対象者
- 本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に配偶者加給年金が支給されている場合
- 加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている場合
経過措置は配偶者加給年金が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となった時のほか、次の場合に終了となります。
- 本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
- 配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき(失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
- 配偶者が、年金選択により他の年金の支給を受けることとなったとき
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.4.4UP
令和4年度の年金額の改定
国から支給される公的年金は、物価や賃金などの変動に合わせて毎年度改定されました。
令和3年の対前年消費者物価指数は、▲0.2%となり、対前年度名目手取り賃金変動率が▲0.4%でした。
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、新規裁定の年金額と受給中の年金額ともに「名目手取り賃金変動率」を用いることが法律で定められています。このため、令和4年度年金額は、名目手取り賃金変動率の▲0.4%で改定されることになりました。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。マクロ経済スライドの未調整分の▲0.3%、は翌年度以降に繰り越されます。
この改定された年金額の振込は、原則6月 (4・5月分)からとなり、年金額の改定通知と振込通知が一体化された「統合通知」が年金受給者に送付されます。
| 年金 | 年金額 (円) | 加給・加算 | 年金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 777,800 | 配偶者加給年金 | 223,800 |
| 遺族基礎年金 | 777,800 | 子の加算 | 223,800 |
| 遺族厚生年金 中高齢寡婦加算 |
583,400 | 子の加算(3人目以降) | 74,600 |
| 障害基礎年金(2級) | 777,800 | ||
| 障害基礎年金(1級) | 972,250 | ||
| 障害厚生年金3級(最低保障) | 1,166,800 |
また、令和4年度の年金生活者支援給付金も改定されました。
65歳以上の老齢基礎年金受給者で非課税世帯であり、令和4年の収入が、881,200円以下の方には次の式で計算した支援給付金が受給できます。
保険料納付済み期間に基づく給付月額は、「5,020円×保険料納付済み期間/480月」
保険料免除期間に基づく給付月額は、「10,802円×保険料納付済み期間/480月」
で計算されます。
なお、収入が881,200円~781,201円の方は、調整支給率をかけた「補足的年金生活者支援給付金」を受給できます。
| 基礎年金 | 月額(円) |
|---|---|
| 遺族基礎・障害基礎年金(2級) | 5,020 |
| 障害基礎年金(1級) | 6,275 |
年金額統合通知書(年金額振込通知と改定通知が一体となったもの)
「年金額統合通知書」とは、毎年6月に年金受給者あてに送付される「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったものをいいます。「年金額改定通知書」とは、法律の規定により物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定された年金額の通知、「年金振込通知書」とは、6月から翌年4月(2か月に1回)まで、毎回支払われる金額の通知です。2つの通知書が1つのはがきで送付されます。なお、2つ以上の年金を受けている場合は、年金種類ごとの通知書が封書で送付されます。
(1)年金額改定通知書
4月に改定された国民年金(基礎年金)と厚生年金のそれぞれの基本額、支給停止額、年金額の各金額とその合計額が通知されます。
(2)年金額振込通知書
4月に改定された年金額の最初の振込月が6月なので、6月上旬に1年分の「年金振込通知書」が送付されます。振込通知書の内容は、年金支払額(1回に支払われる年金額(控除前))とその年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)および個人住民税額が通知されます。特別徴収される額等の詳細についてはお住いの市区町村に問い合わせます。
所得税は、支払額から社会保険料と扶養親族申告書による各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額となります。社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額です。2月期の支払い欄が設けられているのは、各期支払額において1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てて振り込まれます。その切り捨てた端数の合計額が加算して支払われるからです。
なお、「参考:前回支払額」とは、前回の定期支払月(偶数月)に支払った金額の内訳(年金支払額や特別徴収された介護保険料額等)を比較することで年金振込額の増減の理由を確認できるよう設けられました。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.3.8UP
令和4年度の年金額
総務省から、「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたのを踏まえ、令和4年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和3年度から 0.4% の引き下げとなります。
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。
このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動 率(▲0.4%)に従い改定されます。 また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。
令和4年度の改定率は0.996となり、満額の老齢基礎年金(満額)は777,800円となります。令和4年4月分の年金(6月15日の振込)から適用され、日本年金機構からは、年金額の改定通知と振込通知が一体化された「統合通知」が受給者あてに送付されます。共済組合等からの通知は、各共済組合等に確認してください。
| 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 780,900円 | 777,800円 |
| 加給年金・子の加算 | 224,700円 | 223,800円 |
| 子の3人目からの加算 | 74,900円 | 74,600円 |
| 障害基礎年金 2級 | 780,900円 | 777,800円 |
| 障害基礎年金 1級 | 976,125円 | 972,250円 |
| 障害厚生年金(3級)最低保障 | 585,700円 | 583,400円 |
令和4年度の在職老齢年金の支給停止調整額
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止が開始される給与(総報酬月額相当額)と1カ月当たりの年金額の合計額の基準額が28万円から47万円に引き上げられます。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額と直近1年間の賞与の1カ月当たりの額を足したものです。
この改正により、60歳台後半の計算と同じ47万円を支給停止基準額として計算されることになります。
改正により、令和4年4月分の年金額(6月15日の振込)から適用され、支給停止額が変更となる受給者には、日本年金機構からは「支給額変更通知書」が送付されます。
| 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|
| 60歳台前半支給停止調整(開始)額 | 28万円 | 47万円 |
| 60歳台前半支給停止調整変更額 | 47万円 | 廃止 |
| 60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額 | 47万円 | 47万円 |
手当額の改定
物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている次の手当などは、令和3年の物価変動率(▲0.2%)に基づき、0.2%の引き下げとなります。
| 令和3年度 | 令和4年度 | ||
|---|---|---|---|
| 特別障害給付金 | 1級 | 52,450円 | 52,300円 |
| 2級 | 41,960円 | 41,840円 | |
| 年金生活者支援給付金 | 老齢(注) | 5,030円 | 5,020円 |
| 障害1級 | 6,288円 | 6,275円 | |
| 障害2級 | 5,030円 | 5,020円 |
(注)老齢基礎年金による年金生活者支援給付金額は、基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間などに応じて算出されます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.2.4UP
Q 夫(67歳、老齢年金受給者、国民年金の納付期間15年、厚生年金加入期間10年加入)が病気で亡くなりました。妻(60歳)は現在厚生年金加入中です。夫婦2人とも外国籍で、平成元年に来日し日本に居住しています。子供はいません。この場合、遺族年金が受給できるでしょうか?
受給者の死亡(長期要件)による遺族年金と未支給の請求手続き
死亡した老齢厚生年金の受給者によって生計を維持されていた遺族には、遺族厚生年金が支給されます。外国籍の方の場合は戸籍の代わりに、相談者の場合、死亡者と請求者それぞれの属する国の公的機関が発行した戸籍謄(抄)本に代わるべき証明書と世帯全員の住民票が必要です。
もし、それが取れないときは、「続柄」が確認できるものとして死亡者と請求者の「外国人登録原票」の開示請求をしたものか請求者の属する国の公的機関が発行した結婚証明書等を提出します。
「外国人登録原票」
平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理されています。なお、自分の外国人登録原票(写し)の交付を希望する場合、開示請求を行う必要があります。
開示請求ができる方は、当該外国人登録原票に記録された個人情報の本人または、本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当)のいずれかに限られています。任意代理人による請求はできません。なお、死亡者の外国人登録原票の交付も請求できますが、死亡の当時における同居の親族か配偶者(事実婚・内縁含む)直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹に限られます。未成年者又は成年被後見人の取り扱いは、本人と同様です。
外国人登録原票の写しは、請求者本人が出入国在留管理庁に来庁するか、郵送での交付も可能です。詳細は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係にお尋ねください。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2022.1.5UP
年金の給付や健康保険の被扶養者の認定において、「生計維持」要件を満たす必要があります。また「生計同一」要件を満たせばよい場合もあるので、この違いについて見ていきます。
結論から言えば、「生計維持」では、「生計同一要件」と「収入要件」の両方を満たす必要があり、「生計同一」では、収入要件は問われないという違いです。
年金の給付において「生計維持」要件が必要な主なものは、次の例があります。
- 老齢基礎年金の振替加算
- 老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金
- 障害基礎年金の子
- 遺族厚生・遺族基礎年金の受給者
- 寡婦年金の受給者(妻)
次に、 「生計同一」を満たしていればよいものは、「未支給年金」があります。
では、具体的な「生計同一」要件と認められるのは次の例です。
- 住民票上同一世帯の場合
- 住民票上の世帯は別であるが住所が住民票上同一世帯の場合
- 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし、家計も同一の場合
- 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信が交わされている場合
同居が前提条件ですが、単身赴任や施設入所等、別居であっても、経済的援助や定期的な音信を受けていれば、認められます。
収入(所得)要件は、収入または所得が一定の基準以下であることです。その際、相続等一時的な収入・所得は除外されます。
前年(前年分が確定していないときは前々年)の収入が850万円未満もしくは所得が655.5万円未満である場合です。ただし、その時点で該当しなくても、近い将来(概ね5年)以内に該当することが見込まれる場合も認められます。この場合は、就業規則等(退職規定、再雇用後の報酬等がわかるもの)を添えて、収入要件の審査を受けます。
ちなみに、健康保険の被扶養者の認定基準にも「主として生計維持」という要件があり、通常の年金給付の「生計維持」要件との違いは、収入額です。
一般的には、次の基準ですが、健保組合等で異なる場合があります。
<同居の場合>
被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または一定以上の障害が認められる者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満。
<別居の場合>
被保険者からの仕送り等の援助額が被扶養者の年収を上回る場合
収入面において、被保険者に依存している状態であると認められるときに、「主として生計維持」があることになります。
なお、「事実婚(内縁)」である場合は、それぞれの戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得の証明等とその他、保険者が求める書類等(生計同一申立書等)を提出し、診査を受けます。マイナンバーでの届出により、住民票や所得証明書が省略できる場合があるので、詳細は年金事務所・健保組合等に確認しましょう。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.12.1UP
障害年金は、非課税所得ですが、被扶養者の認定においては、収入となります。具体的な例でみていきます。
1 障害年金の税金、障害者控除との関係
障害年金(障害基礎年金・障害厚生・障害共済年金)は、非課税ですが、老齢年金は「雑所得」として、所得税の対象となります。また、老齢年金受給者が、厚生年金に加入していると、総報酬月額相当額と基本月額とで、年金額の調整 (在職老齢年金) があります。障害年金は、同一の事由による傷病手当金との調整はあるものの、報酬との調整はありません。ただ、納付要件の問われない無拠出の障害年金 (20歳前の障害年金等)は、毎年10月に、所得に応じて、年金の支給額の調整があります。
年末調整や確定申告時の「障害者控除」の適用について、障害年金を受給しているだけでは該当しません。国税庁のHPに、障害者控除の対象となる(所得税法施行令第10条に規定)のは、次のいずれかに当てはまる人となっています。詳細は、税務署に確認しましょう。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(以下省略)
2 障害年金の収入・健康保険の被扶養者の認定との関係
健康保険の(協会けんぽ)の被扶養者認定の基準として障害年金額が180万円以上の場合、または障害年金と他の収入が年額180万円以上となる場合は、健康保険の被扶養者になれません。配偶者が被扶養者から外れた場合は、自分で国民健康保険に加入すると同時に、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更となります。
国民健康保険料(税)の額は、自治体により算出方法が異なるので市区町村の窓口で相談します。国民年金保険料は、障害基礎年金を受給 (障害年金等級が2級以上)) していれば、法定免除となります。市区町村の窓口に年金証書等を持参して「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の手続きをします。法定免除を受けた期間の老齢年金額の計算については、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2の割合で計算されます。ただし、平成26年4月以降、将来、老齢年金を受給する可能性があるなどの理由で、保険料の納付を希望する場合、届書にその旨を記入して提出し、保険料の納付が可能です。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.11.1UP
改正の経過
障害基礎年金及び障害厚生年金に係る障害等級の基準は国年令別表等に規定しているところですが、視覚障害に係る障害等級の基準については、平成24年の障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合で検討課題とされ、平成30年7月に行われた身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準の見直し内容等を踏まえて、基準の見直し案が検討されてきました。その結果、令和3年5月の専門家会合において、「視覚障害に係る障害等級の基準の見直し案」がとりまとめられました。
主な改正は、視力の認定基準が、良い方(1眼)の視力に応じて適正に評価できるよう、 「両眼の視力の和」から「良い方の眼(1眼)の視力」による基準に変更されます。また、視野の認定基準も、これまでの「ゴールドマン型視野計に基づく認定基準」に加えて、現在広く普及している「自動視野計に基づく認定基準」が創設されます。この改正は、令和4(2022)年1月1日施行(予定)となっているので、施行後は、診断書の様式も見直されるので、注意が必要です。
国年令別表等に規定する視覚障害に係る障害等級の基準の改正(予定)の概要
- 国年令別表における障害等級1級の基準の改正を受けて、国年則第33条の2の2第1項各号及び厚年則第47条の2の2第1項各号に掲げる障害の状態のうち、視覚障害に係る部分が次のとおり改正されます。
- イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 国年令別表における障害等級2級の基準の改正を受けて、厚年則第47条の2の2第2 項各号に掲げる障害の状態のうち、視覚障害に係る部分が次のとおり改正されます。
- イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- ニ ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
- ホ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.10.14UP
1 在職中の老齢年金制度の見直し (60歳から64歳)
特別支給の老齢厚生年金の在職老齢年金制度の支給停止が開始となる基準額(標準報酬相当額と基本月額の合計)が28万円から47万円 (令和3年度額)に引き上げられます。 これにより、現在、年金が停止されていても、令和4年6月の支払いから一部または全部が支給されるようになる方がいます。
2 在職定時改定の導入 (65歳以上)
現在、老齢厚生年金の受給権を取得した後に厚生年金の被保険者としての期間があるときは、退職時または70歳到達時に年金額の改定が行われています。改正後は、在職中であっても、65歳以降の厚生年金被保険者期間に基づき、毎年 1回改定され、10月分から反映されます。 この在職定時改定により、厚生年金の被保険者期間が240月以上となったときは、その時点での生計維持関係に応じて、加給年金の加算や停止及び振替加算の加算や不該当の改定も行われます。
3 受給開始時期の選択肢の拡大
- 繰上げによる減額率の見直し (法律施行日の前日時点で60歳に到達している方は対象外)
現在、繰上げた場合の減額率は、1か月につき0.5%ですが、昭和37年4月2日以降に生まれた方から、減額率が、1か月につき0.4%となります。 - 繰下げ受給の上限年齢の引き上げ(法律施行日の前日時点で70歳に到達している方は対象外)
現在、繰下げ受給の上限年齢は、70歳ですが、昭和27年4月2日以降に生まれた方から、75歳まで(120月)繰下げることが可能です。なお、繰下げの増額率は変更なく、1か月につき0.7%です。
4 加給年金の支給停止ルールの見直し
現在、加給年金の対象者である配偶者(被保険者期間が240月以上)が、特別支給の老齢厚生年金の受給者でも、在職等で年金の全額が支給停止されている間は、加給年金が支給されます。しかし、令和4年4月以降、このような、被保険者期間が240月以上の配偶者の年金が全額停止されていても、加給年金は、支給されません。
ただし、施行日時点で加給年金を受けている場合は、65歳になるまで等一定の条件に該当するまでは、その支給が継続されるという経過措置が設けられています。
法改正時の変更は、原則、受給者からの届出等ではなく、年金機構等から年金額の変更等の通知が送付されると思いますが、詳細については、年金事務所にご相談ください。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.10.1UP
現在、健康保険の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算し、最大1年6か月ですが、共済組合等では実際に支給された日を通算して1年6か月と異なっています。
令和元年度の協会けんぽの傷病手当金の請求疾病には、精神・行動の障害や新生物(がん)を理由としたものが多く、治療のために入退院を繰り返すなど、長期間に渡って、療養のため休暇を取りながら働くケースが多くみられ、1年6か月の間に一時的に復職した期間についての傷病手当金は不支給となっています。
そのような状況の中で、治療と仕事の両立できるように、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるよう、より柔軟な生活保障のため、共済組合等同様、健康保険の傷病手当金の支給期間も「通算して1年6か月」と改められます。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)が成立し、傷病手当金の支給期間の通算化は、令和4年1月1日に施行されます。
現行では、傷病手当金の支給期間が1年6か月で終了して障害年金の請求へ移行する継続性がありますが、改正後は、いつまでに請求するという上限なしで、通算1年6か月となることで、社会的治癒や再発の取り扱いや年金との併給調整など、どのような影響が出てくるのでしょうか。
ご存じのように、年金との併給調整では、傷病手当金を受けている方が、同一の疾病又は負傷等により障害年金もしくは障害手当金の支給を受けるとき、又は老齢年金の支給を受けるときは、年金が優先的に支給され、傷病手当金で併給調整が行われています(健康保険法第108条第3項~第5項)。
具体的に、受給する障害厚生年金の額(同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額)を360で除して得た日額が傷病手当金の1日当たりの額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。同様に、資格喪失後の傷病手当金と老齢厚生年金も併給調整が行われます。
協会けんぽで、傷病手当金を申請する時、年金証書等(年金額がわかるもの)を添えて、年金を受給していることを申告すれば、調整された傷病手当金が支給されます。一方、傷病手当金の申請時には年金受給権がなく、傷病手当金を受給していて、その後年金が決定された場合は、遡って併給調整が行われ、過払いとなった傷病手当金を返納することになります。
今後、障害年金受給者が傷病手当金を請求するケースの対応にも注目していく必要があるでしょう。
厚生労働省HP参照
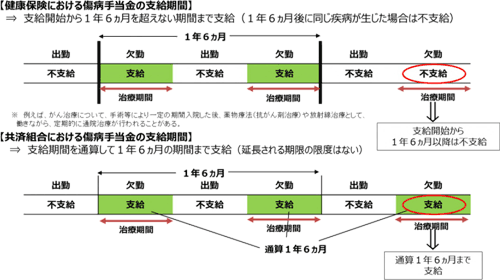
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.9.22UP
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度下がった場合を理由とした国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例の申請手続きが、令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)も延長されています。
この臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予申請は、以下の2点のいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
臨時特例による免除の申請に必要な書類は次の2つの書類(年金機構のHPから取得可能)となりますが、免除の申請する期間によって、「所得申立書」の年度が異なるので年金事務所に確認しましょう。
免除の申請書は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送します。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構のホームページ)
- 所得の申立書(日本年金機構のホームページ)
なお、免除、納付猶予の承認を受けた時は、保険料を納付した場合と比べて将来の老齢年金額が低くなります。免除等の承認から10年以内であれば、追納することも可能です。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.9.15UP
障害年金の請求は、請求者本人の死亡後、一定の条件を満たせば、遺族の方が「障害年金の未支給」として請求できる場合があり、原則、通常の障害年金請求と同様に次の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 障害の原因となった病気やケガの初診日においての国民年金・厚生年金等に加入している要件(20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。)
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと等保険料の納付・免除している要件
- 障害認定日(事後重症の場合は請求日)において一定の障害の状態にある要件
異なる点は、本人が死亡した後の請求は、「事後重症請求」ができず、「認定日請求」でなければならないことです。認定日に障害等級に該当した場合に、障害認定日の属する月の翌月から本人が死亡した月までの障害年金が、未支給年金として遺族に支給されます。
日本年金機構への手続きは、障害年金請求書と未支給年金請求書に必要書類を添えて同時に提出しますが、認定日の診断書を提出できるか、またそれが障害等級に該当するかが一番のポイントになります。
認定日とは、初診日から1年半もしくはそれ以内に症状が固定した日ですが、死亡した方が、認定日から3ヶ月以内にその傷病で医療機関を受診していていることが必要です。受診していれば、医師に認定日から3か月以内の日での診断書を依頼します。ただ、受診していても、診断書に必要な検査・計測のデータ不足や、心電図やレントゲンの添付が不可など、診断書の記載内容が不備だと障害状態の審査ができません。また、認定日が5年以上遡及となると、カルテが処分されていたり、医療機関自体が廃院していたりで、診断書の提出すらできず、請求自体もできません。
未支給請求できる遺族は、生計同一関係にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他①~⑥以外の三親等内の親族となり、未支給の請求の時効は、死亡から5年です。なお、死亡した方が2級以上の障害厚生年金受給者と認定され、一定の条件を満たす遺族がいれば、遺族厚生年金(短期要件)が支給される場合もあるので、詳細は、年金事務所に相談することを勧めます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.8.26UP
健康保険法等における傷病手当金の扱いについて
新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病にかかっている場合と同様に、健康保険や共済組合に加入されている方であれば、療養のために3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている場合に傷病手当金が支給されます。
支給額は、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。なお、労務に服することができなかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、医療保険者において労務不能と認められる場合(被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」 と判定され療養のため労務に服することができない場合等)があります。
また、国民健康保険(国保組合加入者を含む)に加入している方については、市区町村又は国保組合によっては、条例(国保組合の場合は組合規約)により、新型コロナウイルスに感染した被保険者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する医療保険者(市区町村、国保組合)にご確認ください。
また、医療従事者の方などが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。新型コロナウイルス感染症による症状が継続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
令和2年3月6日 厚生労働省通知参照
(ひろべ・まさよし:元健康保険組合常務理事。現在は健保連神奈川連合会、柔道整復療養費相談会・相談員)
2021.8.2UP
第三者行為とは、他者の故意や過失によって引き起こされた行為のことを言い、交通事故による傷病が最も多く、労災事故、電車や船舶の事故、他者から受けた暴行等が原因の場合などがあります。これら、第三者行為による傷病で障害年金を受給した場合、第三者(事故の加害者)からの賠償金と国の年金と二重の補償を受けることになるため、障害年金を一時支給停止にする調整が行われます。
支給停止期間
支給停止期間は、受け取った賠償金を基に、「休業損害」や「逸失利益」等の生活保障に相当する部分のみで計算され、治療費などの実出費や慰謝料などは支給調整の対象にはなりません。また、停止期間は、事故が発生した日から最長でも36ヶ月間です。なお、平成27年9月30日以前に発生した事故の場合の支給停止期間は24ヶ月になります。
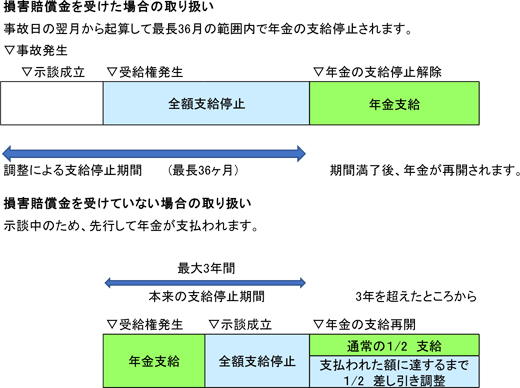
第三者行為届と必要な書類
所定様式(年金事務所から取り寄せます)
- 第三者行為事故状況届
- 確認書 賠償金を受けた場合、年金が停止となることを了承している
- 同意書 日本年金機構が保険会社等から直接情報を受けることの同意
添付する書類 例(事故のケースにより異なります)
- 交通事故証明(自動車安全運転センターに申請。事故が起こった日 から5年以内でないと取得できません)
- 被扶養者がいる場合
扶養していたことを証明する源泉徴収票、健康保険証や学生証の写しなど - 損害賠償金の算定書、示談書等、受領金額がわかるもの
- 示談書(写)
なお、第三者行為は、労災なら、労働基準監督署へ、医療保険なら加入している制度(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険等)へもそれぞれ手続きが必要となるので、詳細は、担当部署に確認しましょう。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.7.15UP
手足の切断や失明、人工関節の挿入置換のように障害状態が固定された場合、永久固定と認定され、障害状態確認届(診断書)の提出はありません。ただし、障害の程度が悪くなった場合、自ら「額改定請求」を提出する必要があります。
これに対し、有期認定は、1年から5年以内の期間(更新期間)の範囲で、障害の程度の再確認のため、障害状態確認届(診断書)の提出が求められています。
人工透析をしている場合は、原則、有期認定となりますが、合併症がなく、症状が安定している場合は、有期5年となり、また、70歳以上の受給者の場合は、永久固定になります。
令和元年8月以降、20歳前傷病の障害年金の受給者も、障害状態確認届(診断書)の送付が、誕生月の3か月前の月末となり、誕生月の末日までの現症日で提出するように変わりました。
障害状態確認届でチェックポイント
(1)診断書の種類と枚数は一致していますか?
脳血管疾患の傷病で障害年金を肢体麻痺と高次脳機能障害で認定された場合、障害状態確認届(診断書)は、肢体と精神の2種類の診断書が必要です。
(2)障害状態確認届の現症日は、指定日のものですか?
誕生月の3か月前から誕生月の末日までの現症日であるか確認が必要です。
障害状態確認届(診断書)の審査で等級が下がる場合
(1)障害認定基準の改正があった場合
改正後の障害認定基準に基づいて審査されるため、障害の程度が障害等級に該当しなくなることがあり得ます。
(2)就労していて障害の程度が軽くなったと認定された場合
精神の診断書には、就労状況を記入する欄があり、就労していれば障害が軽くなったと判断されることがあります。
医師に記入を依頼する際に、障害者雇用枠であり、周りの人からの支援の内容など就労の形態や状況を詳しく書いてもらうようにします。
障害状態確認届(診断書)に額改定請求書を同時に提出する場合
障害給付額改定請求書」を付けない場合は、更新時に等級が上がらなくても不服申立てをすることができません。不服があったときは、改めて「障害給付額改定請求書」に診断書を添えて請求する必要があります。 「障害給付額改定請求書」を付けた場合は、「障害給付額改定請求書」に対しての決定事項である、「等級が改定されなかった」ことに不服申立て(審査請求)をすることができます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.7.1UP
障害の程度を認定する基準は、国年令別表、厚年令別表第1及び別表第2に加え、「障害等級認定基準」に定めるところによるものとされています。また、これらに、明示されていない障害については、医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行うこととされています。具体的な事例として、4つの傷病(繊維筋痛症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、脳脊髄液漏出症)の診断書が「認定困難事例」として年金機構のホームページに掲載されています。
『線維筋痛症』
線維筋痛症とは、原因不明であらゆる検査でもほとんど異常が認められず、全身の疼痛を主症状とし、精神神経症状(不安やうつ病など)、自律神経の症状(過敏性腸症候群)を副症状とする疾患で、長時間に渡る疼痛のためQOL(生活の質)が著しく低下します。「線維筋痛症の重症度分類試案」(厚生労働省研究班)により、ステージ1~ステージ5に分類されているので、肢体の診断書には、このステージ数の記載が必要です。
『慢性疲労症候群』
慢性疲労症候群とは、原因不明の全身倦怠感が急激に始まり、十分な休養をとっても回復せず,長期にわたり疲労を中心に微熱、のどの痛み、リンパ節のはれ、筋力低下、頭痛、精神神経症状などが続き、日常生活に支障をきたす疾患です。慢性疲労症候群は旧厚生省研究班の重症度分類でPS O~PS 9に分類されているので、肢体の診断書には、この重症度分類が記載が必要です。
*PS=Performance status(パフォーマンス・ステータス)
『化学物質過敏症』
化学物資過敏症は、化学物質の暴露(ばくろ)が個人の許容量を超えると、その後も原因となる化学物質の微量暴露であっても免疫障害、自律神経障害、精神障害、臓器障害などのアレルギー疾患または中毒的な多種類の体調変化をきたし、化学物質に対して過敏状態となる疾患です。化学物資過敏症は、診断書以外に「障害年金の請求にかかる照会について」(所定の用紙)を医師に記入してもらい提出します。
『脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)』
「脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)」とは、交通事故や転倒など頭部への強い衝撃で脳や髄液を覆う硬膜に穴があき、脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって、脳脊髄液が減少し、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠・易疲労感などを引き起こすと考えられている疾患です。請求者の症状が正しく反映されるように、「その他診断書」「肢体の診断書」のいずれの診断書でも提出可能ということになっています。
以上、明示されていない障害についても認定されていますが、以前から 違法薬物の使用によって生じた障害であると医学的に認められた場合は、国年法70条、厚年法73条の2より、障害年金の全部または一部が給付制限となっていました。今般、今までの認定事例に基づいて、令和3年3月4日、年管管発0304第6号 厚生労働省年金局の通知で「給付制限の取り扱い」が整理されました。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.6.1UP
健康保険の資格を取得した日から傷病手当金や出産手当金の請求が来たら担当者はびっくりするでしょう。誰も病気や出産休業中の人を雇用する人はいないからだ。
実は、健康保険組合が解散し協会けんぽに移ったり、適用事業所が一括適用になったりすることで、健康保険の記号番号が変わる場合がよくあるが、次のように共済組合員への移行もあるのだ。
国家公務員や地方公務員の場合は、いわゆる正規職員は共済組合員となるが、非常勤職員(短時間勤務のアルバイト等)は、協会けんぽの被保険者【注1】となる。しかし、12カ月以上勤務する常勤的な臨時職員は、政令によって正規職員と同様にみなされ共済組合員となる。一年以上勤務した時点から共済組合員になるわけだ。
健康保険法には共済組合に関する特例【注2】があり、元の保険者である協会けんぽが資格喪失後の給付として支給するのではなく、共済組合が資格取得日から出産手当金を支給すべきと解釈できる。実際にあった事例では、協会けんぽが紳士的な対応で被保険者期間が1年以上あるので資格喪失後の給付として支給することを表明したが、腑に落ちないのは関西地方にある共済組合側の対応で、これは法律の盲点だと云って支給を拒否したらしい。法令に基づき保険者が移動しただけで、逆選択でも何でもない。健康保険組合が解散し協会けんぽに移った後で、直ちに被保険者から出産や傷病手当金の請求があっても時効でない限り協会けんぽが支給している。健年タイムス第12号でも述べた通り、無慈悲な保険担当者が誤解しないためにも医療保険制度間の調整は法律で明確にすべきだ。
【注1】令和4年10月1日から短時間勤務者も短期給付の共済組合員となる。
【注2】共済組合に関する特例(健康保険法第二百条)国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
(ひろべ・まさよし:元健康保険組合常務理事。現在は健保連神奈川連合会、柔道整復療養費相談会・相談員)
2021.5.1UP
日本年金機構での障害年金の請求では、障害の原因となる傷病の初診日を特定するために、診断書作成の医療機関と初診時の医療機関が異なるときは、「受診状況等証明書(初診日証明)」の提出が求められています。
それというのも初診日に加入していた制度で「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かが決まるからですが、遡及請求の時など、廃院やカルテの処分により、初診日の証明を得ることが困難な場合があります。その時は「受診状況等証明書を添付できない申立書」に診察券や領収書等の参考資料を添えて、初診日を申し立てることになります。
まず、20歳以降に初診日がある場合は、次の書類を提出します。
(1)第三者証明2通と参考資料
または(2)初診日頃に受診していた医療機関の医療従事者による第三者証明1通
第三者証明とは、請求者の友人・知人など3親等内の親族以外の方が、初診日頃の状況を直接見て認識していたことや請求者や家族から、聞いていたことを記入した申請書であって、複数の方により作成された2通が必要です。
それに、添付する参考資料の例としては、診察券や領収書以外に、生命保険・労災保険の給付申請時の診断書、障害者手帳申請時の診断書などがあります。他にも、医療情報サマリー(入院・外来患者の診療経過)や健康保険協会や健康保険組合から開示請求で取り寄せた給付記録(レセプト含む) などがあります。 なお、当時の担当医師や看護師等医療機関の医療従事者による第三者証明であれば、参考資料を添えず、1通だけで十分です。
次に、20歳前に初診日があるときは、先の1と2に加え特例として、2番目以降に受診した医療機関が作成した「受診状況証明書」や「診断書」の記載内容で、明らかに障害認定日が20歳到達以前であることが確認できて、その受診日の前に厚生年金の加入期間がないときは、1番目の医療機関の証明の提出を省略することが可能です。
その他、第三者証明ではなく、初診日がある一定期間の「始期と終期」を示す書類を提出し、初診日を申立てることもできます。具体的には「受診状況等証明書を添付できない申立書」と「始期」の例として、就職時の健康診断書や発病していないことが確認できる人間ドックの結果など、「終期」の例として、 2番目以降に受診した医療機関の証明や交付日の記載された障害者手帳などを提出します。それにより、初診日が一定期間内にあることが確認され、その期間のいずれの時点でも納付要件を満たしているなどの条件を満たせば、請求者の申立ての日が初診日と認められます。
初診日の証明が取れない時でも、第三者証明や初診日が存在する期間の証明及び客観的な参考資料等の提出により、初診日の審査が行われています。様式等詳細は日本年金機構のホームページをご参照ください。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.4.2UP
障害年金の障害等級を認定する日(障害認定日)は、国年法第三十条・厚年法第四十七条により、「初診日から1年6か月を経過した日」とされていますが、同条では、「初診日より1年6か月の期間内にその傷病が治った(その傷病が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)ときはその日」としても定めています。
具体例には、①器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している切断日や人工関節の挿入置換日等の場合、または②その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った人工透析等の場合があります。
脳血管疾患の認定日については、平成24年9月に、「障害認定基準 第9節/神経系統の障害 神経系統の障害による障害の程度」で改正されています。(以下抜粋)
脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。(中略) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6か月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。 ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
これにより、6か月経過すれば、神経系の障害での障害年金の請求が可能ですが、無条件で認められるものではなく、審査の上、固定と認められなければ1年6ヶ月を経過してからの請求となります。 6ヶ月固定での請求は、肢体の診断書で「治った日の欄」及び「予後の欄」に、症状固定の日付や、機能回復訓練(リハビリ)の終了等の記載内容により審査されます。
高次脳機能障害を併発していても、精神の診断書では、症状固定と認められません。そのため、6か月固定での請求で、肢体の等級が2級以下で認定された時は、1年6ヶ月経過した時に、精神の診断書と額改定の請求をすることになります。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.3.29UP
被保険者期間が1年以上ある被保険者が資格喪失後6カ月以内に出産した場合には、「出産育児一時金」という長い名称の給付が出生児数に応じて支給される。
私が健保の役員時代、既に他の健康保険から給付を受けていた場合に、不支給にすべき根拠についてよく質問を受けたが、法令上の明確な規定は見つからない。
健康保険法上の歴史的経過は省くとして、出産育児一時金【注1】は、以前「分娩費」と「育児手当金」とに分かれていて、死産(流産【注2】)のときには育児をしないから育児手当金は支給されなかった。また、分娩費は標準報酬月額の1ヵ月分であった。そのため、資格喪失後の分娩費の額が多い人は、配偶者分娩費と本人分娩費のうち有利な給付【注3】を選択して受給することが普通であった。
皆保険が進み、国民健康保険制度の充実で傷病手当金、出産手当金を除けば、資格喪失後の保険給付の存在意義が薄れている。むしろ、保険者間の調整事務【注4】や法令上の根拠を被保険者に説明する手間を考えれば、次期改正時に改正して頂きたいものだ。古い話で恐縮だが、私が全総協【注5】の医療対策委員だったとき、この改正と併せて名称を「出産費」としてほしいと、厚生労働省に要望してきたがいまだに改善されていない。
ところで、冒頭の質問の回答であるが、「一つの保険事故で二つの保険給付を受けられない。保険者が異なっていても重複して給付を受けることは公序良俗に反する。」という訳だが、皆さんがにわかに納得してくれると有り難い。
コロナ禍で子供を産むことが命がけになっている昨今、民間病院で出産した場合は法定給付の一時金だけでは出産費用をすべて賄えないのが実情だ。政府は少子化対策で不妊治療の保険適用を決めたが、もっと優先的に改善すべき事項があるのではと思う。
【注1】国及び地方の各共済組合法による一時金は「出産費」という判りやすい表現である。
【注2】日本産科婦人科学会は、妊娠22週(6カ月)より前に妊娠が終わることを流産(12週未満は早期流産、12週以降22週未満を後期流産)、そして22週以降を死産としている。なお、出産育児一時金は妊娠12週(84日)を超えて出産(死産を含む)した場合を対象としている。
【注3】出産育児一時金及び埋葬料に係る喪失後の給付にも付加給付がある健康保険組合の場合は有利な保険者の給付を選択する場合があるので調整が煩わしくなる。また、直接支払制度が導入されたことで、元の健康保険組合から付加給付だけ受けたいという人もいて、担当者を悩ませる。
【注4】日雇特例被保険者として同一の給付を受けている場合はその額の範囲内で家族出産育児一時金は支給されない(法54条)、また、資格喪失後の給付は船員保険の被保険者となったときは船員保険が優先するので健康保険からは支給されない(法107条)。
【注5】全国総合健康保険組合協議会の略
(ひろべ・まさよし:元健康保険組合常務理事。現在は健保連神奈川連合会、柔道整復療養費相談会・相談員)
2021.3.1UP
日本年金機構におけるマイナンバーの利用について
平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令」が公布・施行され、日本年金機構でも、マイナンバーと基礎年金番号を紐付けて、国民年金や年金給付等の手続きが行われています。
平成30年3月5日からは、マイナンバーの利用で、日本年金機構へ被保険者や受給者の氏名変更届や住所変更届及び死亡届が原則不要となりました。遺族年金の受給者の氏名変更の理由が「婚姻」や「養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合を除く)」の場合、遺族年金が受けられません。その時は「遺族年金失権届」、それ以外の理由の場合は「遺族年金受給権者氏名変更理由届」の提出が必要です。
令和元年7月1日からは、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、従来、年金請求の際に生計同一・維持の確認のため戸籍謄本、住民票、所得証明書を提出する必要がありましたが、住民票と所得証明書の添付を省略できるようになりました。ただし、戸籍謄本は、情報連携の対象外のため、引き続き提出が求められます。
また、情報連携で確認できる住民票は平成29年4月1日以降、課税・非課税証明は平成29年度以降のものとなります。遡及請求で平成29年4月1日以前の状況を確認する必要がある場合などは、従来通り住民票や戸籍の附票などの提出が求められます。
情報連携を活用した具体的な請求手続きについて
特別支給の老齢厚生年金(加給年金か振替加算が有り)を請求する時、戸籍の謄本・抄本と振込口座の通帳の写を添付すれば、住民票と所得の証明の添付を省略できます。雇用保険も情報連携の対象ですが、未だ被保険者証等の写が求められています。
未支給年金の請求時は、届書にマイナンバーを記入して、死亡者と請求者が同居なら、戸籍謄本・抄本と振込口座の通帳の写しで手続きできます。別居であれば「生計同一関係に関する申立書」を追加します。
なお、詳細な必要書類は、年金事務所に相談の予約をする際に確認できます。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.2.15UP
厚生年金保険の被保険者が業務上の理由で障害の状態になった時、障害厚生年金等と労災年金の両方が支給されますが、障害厚生年金等が全額支給され、労災年金が一定の率で減額支給となります。労災年金の調整率は、障害厚生年金等の給付のよって異なります。(表参照)
労災保険では障害等級の第1級~7級は年金として、第8級~14級は一時金として支給されます。労災保険の障害(補償)一時金は、併給調整の対象にはなりません。
障害厚生年金では、1級~2級は障害基礎年金と障害厚生年金、3級は障害厚生年金のみ支給されます。調整された労災年金の額と厚生年金等の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように配慮されていて、労働福祉事業の障害(傷病)特別支給金も減額されません。
労災年金と厚生年金等の調整率
| 労災年金 | 障害補償年金 | |
|---|---|---|
| 社会保険の種類 | 併給される年金給付 | 障害年金 |
| 厚生年金及び国民年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 |
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 0.83 |
| 国民年金 | 障害基礎年金 | 0.88 |
65歳前 特別支給の老齢厚生年金受給者の場合
労災の障害補償年金と障害厚生年金(3級以上)の受給者でかつ、特別支給の老齢厚生年金の受給者が、65際未満で退職し「障害者特例」に該当すると、報酬比例部分に加え、定額部分と加給年金(厚生年金期間が20年以上あり65歳未満の生計を維持している配偶者がいる)が支給されます。障害厚生年金でなく障害者特例(老齢年金)の給付を選択すれば、労災の障害補償年金は減額されず全額支給されます。
65歳以上の老齢厚生年金受給者の場合
労災の障害補償年金と障害厚生年金(2級以上)の受給者でかつ老齢厚生年金受給者の65歳以降の年金の方法には、1 障害厚生年金と障害年基礎年金、2 老齢厚生年金と老齢基礎年金、3 老齢厚生年金と障害基礎年金の3通りの組合せがあります。障害厚生年金等の選択方法により労災の調整率が1は0.73、2は調整なしで全額支給、3は0.88となります。
(ひるた・よしこ:社会保険労務士、FP技能士2級、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、2009年12月、東京社会保険事務局を退職。街角の年金相談センターの相談員として年金相談業務に従事する傍ら、わかりやすい年金の事務手続き等のセミナーや専門誌等への執筆活動を行っている。)
2021.1.12UP
会社を辞めてしまった方の傷病手当金はもう仕事がないにもかかわらず、従前の業務を基準に労務の可否を判断するのはおかしいのではないかという質問をよく受ける。
平成19年4月改正前は、任意継続被保険者中に発病した傷病も傷病手当金の対象となっており、その場合は退職前の業務ではなく、一般的な労務に従事できる場合は傷病手当金を支給しないとしていた。しかし、会社に迷惑を掛けてはいけないと考え、就業規則では退職の必要がないのに自己都合退職する場合もある。
傷病手当金は、「療養のため引き続き勤務に服することができない場合」に支給するのが趣旨であり、必ずしも医学的に労務不能を条件としていない。就労能力があっても歩行困難や通院のため出社できない場合でも対象になる。
他方、国家公務員共済組合の運用方針では、資格喪失後の傷病手当金について、「労働能力がある場合には、「傷病のため勤務に服することができない場合」に該当せず、従って自家営業を行っている場合、事業所に雇用されている場合、勤務することができる状態にありながら、適当な職がないために勤務しない場合等には、組合員資格喪失後の傷病手当金は支給できないものと解される。」となっているが、健康保険法においても同様の解釈が成り立つ。しかし、地方公務員等共済組合の運用方針では、前記の他に、「退職後に継続して支給する傷病手当金は、病気又は負傷のため就労能力を失っている場合に限り支給する。」となっている。(就労不能の判断は医師の意見を確認)
健康保険法では、特に厚生労働省から通知がだされていないが、拡大解釈すると入院中か障害の状態にある場合に限るとも読める。会社に忖度して退職したため、退職日まで支給されていた傷病手当金が翌日から支給されない事態が生じる。
令和4年10月から非常勤公務員の共済組合(短期給付)への加入が施行される予定だが、いままで「協会けんぽ」に加入していた不安定な身分の職員が病気退職後に受ける傷病手当金の支給要件が現行より厳しくなるようで気になるところだ。
(ひろべ・まさよし:元健康保険組合常務理事。現在は健保連神奈川連合会、柔道整復療養費相談会・相談員)


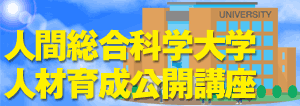
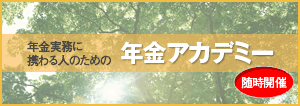

 2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。新年は1月5日(月)より営業いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。新年は1月5日(月)より営業いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。