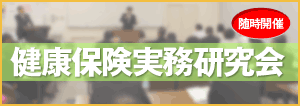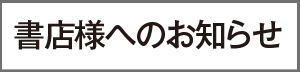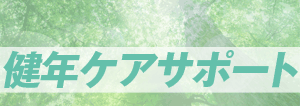2025年度 社会保険トピックス
年金Topics 令和7年度の年金額は1.9%の引上げ
年金額は物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の人の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
令和7年度の年金額は名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて改定します。また、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。よって、令和7年度の年金額の改定率は1.9%となります。
令和7年度年金額の例(月額)
●国民年金
老齢基礎年金(満額) 1人分
昭和31年4月1日以前生まれの人 69,108円(対前年度比+1,300円)
昭和31年4月2日以降生まれの人 69,308円(対前年度比+1,308円)
●厚生年金
夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額
232,784円(令和6年度:228,372円)
※男性の平均的な収入(平均標準報酬〔賞与含む月額換算〕45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金〔満額〕)の給付水準。
年金Topics 令和7年度の国民年金保険料
平成16年の年金制度改正で国民年金の保険料額は毎年引き上げられることになり、平成29年度に上限(平成16年度価格水準で16,900円)に達し、引き上げが完了しました。そのうえで、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の人など)に対する産前産後期間の保険料免除制度が平成31年4月から施行されたことに伴い、令和元年度分より平成16年度価格水準で保険料が月額100円引き上がり、17,000円となりました。
実際の保険料額は、平成16年度価格水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて毎年度改定されます。
令和7年度 国民年金保険料額(月額)17,510円
年金Topics 在職老齢年金の支給停止調整額が50万円から51万円に【令和7年4月~】
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度の支給停止調整額は51万円(令和6年度は50万円)となります。


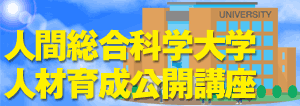
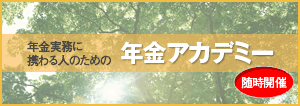

 2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。新年は1月5日(月)より営業いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。新年は1月5日(月)より営業いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。